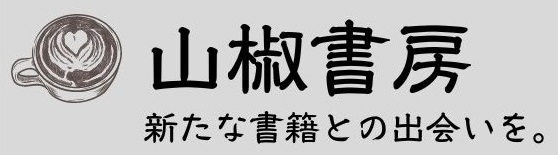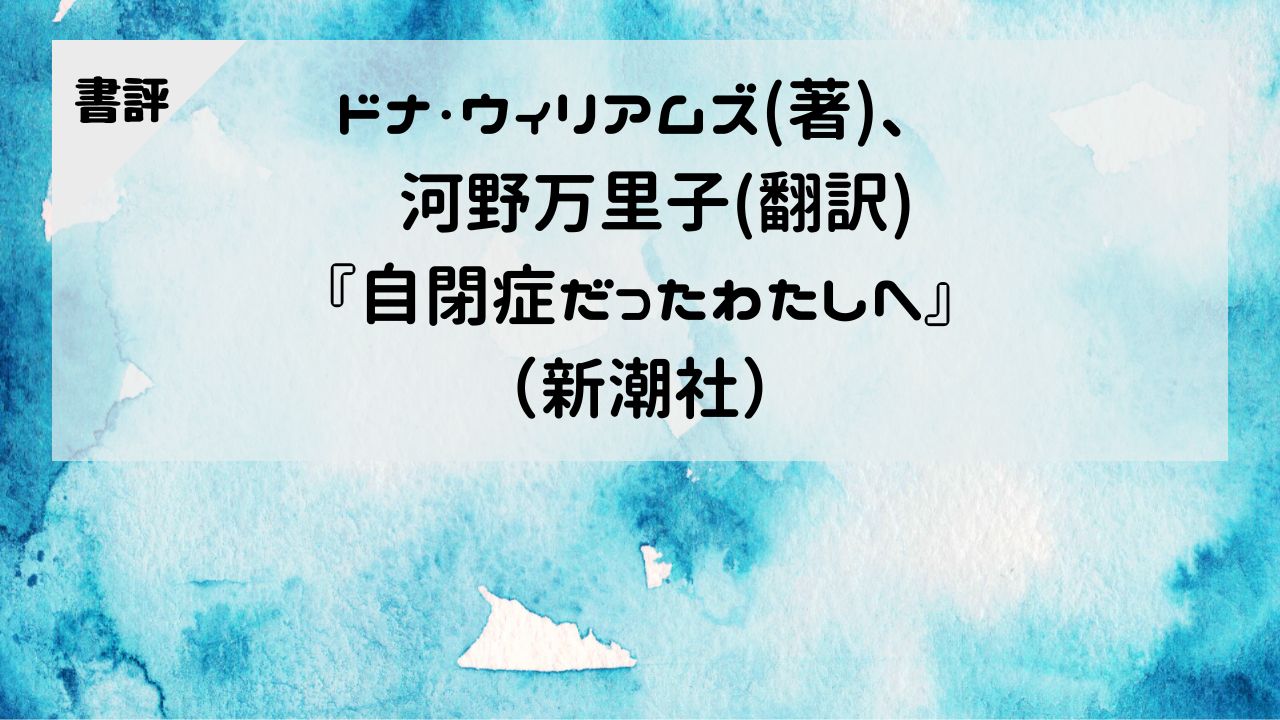日本では、2000年代後半から発達障害という言葉が広く知られるようになりました。2005年に施行された発達障害者支援法以降、「ASD(自閉スペクトラム症:Autism Spectrum Disorder)」「ADHD(注意欠陥・多動性障害:Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)」「LD(学習障害:Learning Disabilities)」の人びとの特徴がさまざまなメディアで公開され、「大人の発達障害」という呼び方も定着しつつあります。当事者への理解が徐々に進んできました。
さて、今回ご紹介するのはこの発達障害の当事者による書籍です。『自閉症だったわたしへ(原題:NOBODY NOWHERE)』は、自閉症(現在では、ASDと呼ぶ)のドナ・ウィリアムズ氏が自身の半生を振り返った手記です。
本書は、おそらくASDの当事者が書いた最も初期かつ有名なエッセイの一つでしょう。ASDとはコミュニケーションの障害と言われており、周囲の人びととうまく会話できなかったり、目の前の相手が考えていることの意図を汲み取ることに困難を感じるとされています。
しかし、本書で綴られるドナ氏の文章からは、ドナ氏が圧倒的な語彙量を有しており、決して知的レベルが低い訳ではない(むしろ、客観的・分析的に自身を見つめている点は知性を感じさせる)ことがわかることでしょう。ページ数は多めで読み手には多少の覚悟が求められます。それでも、世界中でベストセラーとなったということは、それだけ人びとに与えた衝撃が大きかったといえるでしょう。
こんな方にオススメ
- ASDの当事者である
- ASDの当事者が見ている世界を知りたい
- 発達障害児・発達障害者の支援に関わる仕事がしたい
言語コミュニケーション
この頃わたしは、再び聴力テストを受けた。口をきくことはできても、普通の人とは話し方やことばの使い方が違ったり、言われたことに対して何も反応しなかったりすることが多かったので、難聴ではないかと疑われたのだ。確かに言語はシンボルであるが、ではわたしがシンボルというものを理解していなかったかというと、それも違う。わたしにはちゃんと、わたしだけの話し方のシステムがあって、それこそが「わたしの言語」だったのである。まわりの人々こそそういったわたしのシンボリズムを理解していなかったのだし、そんな人々に対して、どうやってわたしの言いたいことを説明したらよかったというのだろう。
引用元:ドナ・ウィリアムズ(著)、河野万里子(翻訳)『自閉症だったわたしへ』(新潮社)
著者は、周囲とまったくコミュニケーションが取れないという訳ではありませんでしたが、いわゆる会話のキャッチボールがうまくできないという状況だったようです。著者が用いる言語と、周囲が用いる言語が異なっている。これは、母国語が異なる人たち同士の会話ですれ違いが生じる状況と少し似ているのかもしれません。
なお、1993年出版時に「序章」の中でオーストラリアの児童心理学博士ローレンス・バータック氏が寄せた文章には以下の記述があります。ASDの症状が知られるにつれて、ASDとの診断を受ける人びとは出版当時と比べて増えているように思えますが、男性の方が当事者が多いという傾向は大きく変わっていないようです。現代ではASDの男女比はおよそ4:1と報告されており、圧倒的に男性の方が多いです。
自閉症は稀にしか発生しないのだが、非常に厄介な障害だ。統計的には、子供一万人のうち四人の割合で発生し、男子に多い。女子は大体自閉症児五人に一人の割合なので、人口六千万人ぐらい――ちょうど英国に匹敵する規模の国――では、自閉症の女性は、あらゆる年代の合計で五千人程度ということになる。一方、社会的生活がおくれないほどの精神障害を持つ女性は二、三十万人いるのだから、自閉症の女性というのがいかに稀な存在か、おわかりいただけると思う。
引用元:ドナ・ウィリアムズ(著)、河野万里子(翻訳)『自閉症だったわたしへ』(新潮社)
精神科医に出会い未来が開けてゆく
著者は、日常的に母親から虐待を受けており、実の兄にも暴力を受けて育ちます。そして、家出をして友人の家に寝泊まりしたりといった経験を何度も重ねた結果、独り暮らしを始めます。
そして、行く先々で出会った男性たちと親密な関係になり、同居します。しかし、ここで幸せな結果となることは極めて稀。男性から暴力を受けたり、わずかな貯金を失うことになったり、自分の判断で相手から離れる決断をしたりと辛い日々が続きます。
そんな中、メアリーという精神科医と出会い、少しずつ未来が開けてきます。休学していた高校に復学し、大学へ進学し、勉学に励みます。勉強を重ねるなかで、自分に合う学問、合わない学問を知り、自己理解を深めていきます。
ASDの当事者だからこそ
本書のなかで最もこころ揺さぶられたのは、著者がASD当事者の男性ショーン氏と再会したあと、再び別れるシーンです。おそらく、多くの読者にとっても大変印象に残る部分だろうと思います。
彼は極めて自閉症的といえる行動をとるのですが、その行動の意味が著者には分かりすぎるほどに分かってしまったのでした。そうした一連の流れを読むうちに、ドナ氏とショーン氏双方に対して、読み手は混乱とともに胸にこみあげるものがあるはずです。
手はがくがくと震え続け、彼はなかなか鉛筆を操ることができなかった。むだな力の込められた鉛筆は、ぶざまに紙を破いた。彼は一人で闘っていた。目からは苦闘の涙があふれ出した。
引用元:ドナ・ウィリアムズ(著)、河野万里子(翻訳)『自閉症だったわたしへ』(新潮社)
彼はぎざぎざに破れた紙の破片に、まるで掻き傷をつけるかのようにして、必死で文字を書きつけた。そうしてその紙切れを荒々しくわたしの手に押しつけると、ぎゅっと拳の中に握らせた。
「行ってくれ。何か起こっちまう前に早く行ってくれ」彼は喘ぐようにそう言うとわたしを押しのけ、乱暴に車のドアを閉めて走り去った。
わたしは震えながらプラットホームに立った。怖くて、彼のくれた紙切れを見ることができなかった。いっそ捨ててしまおうか、とも思った。あまりにもすべてが度を越していた。あまりにもすべてがよくわかった。それはあまりにも、わたし自身だった。
(中略)
街灯の下で、わたしはくしゃくしゃになった紙切れを広げた。するとそこに書きつけられていたことばは、筆跡のぎこちなさをものともせずに、あざやかに立ち上がってきたのである。「きみはぼくが生涯かけて待ち望んでいた最高の友達です。これからも連絡をください」
ショーンとの交流の結末もとてもこころを動かされるものでした。是非、実際に本を手にとってその結末をお確かめください。
ドナ・ウィリアムズ氏のその後
さて、著者のドナ氏は1963年10月12日にオーストラリアで生まれました。この記事を書いている2026年現在に存命なら、60代です。そこで現在の状況を確認したところ、ドナ氏は2017年4月22日にがんにより、53歳でその生涯を終えているようでした。
晩年は、夫のクリス・サミュエル氏と穏やかな日々を過ごしたようです。彼女の訃報に触れたブログ記事はこちらです。
本書が出版されたことで、ASDの当事者への理解は格段に進んだと思いますし、当事者自身に救いをも与えたこととと思います。その功績は測り知れません。
関連書籍
- 東田直樹『自閉症の僕が跳びはねる理由』『自閉症の僕が跳びはねる理由2』(KADOKAWA):私が初めて自閉症当事者が書いた文章を読んだのは、東田さんの著書です。本書では、当事者の方の抱える悩みを垣間見ることができます。小説や詩も掲載されており、その感性に驚かされます。
- 本田秀夫(監修)『自閉症スペクトラムがよくわかる本』(講談社):講談社さんの健康ライブラリーシリーズはイラストが豊富で分かりやすいので、対人支援を中心とした職業に関心がある方にオススメします。
- 宮尾益知『女性のアスペルガー症候群』(講談社):こちらも講談社さんの健康ライブラリーシリーズ。ASDの当事者比率には男女差がありますが、その特徴にも男女差があることがよくわかる一冊です。
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪