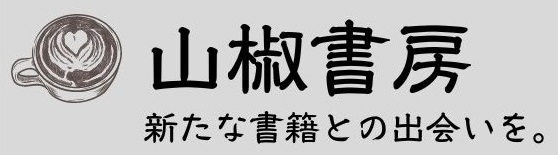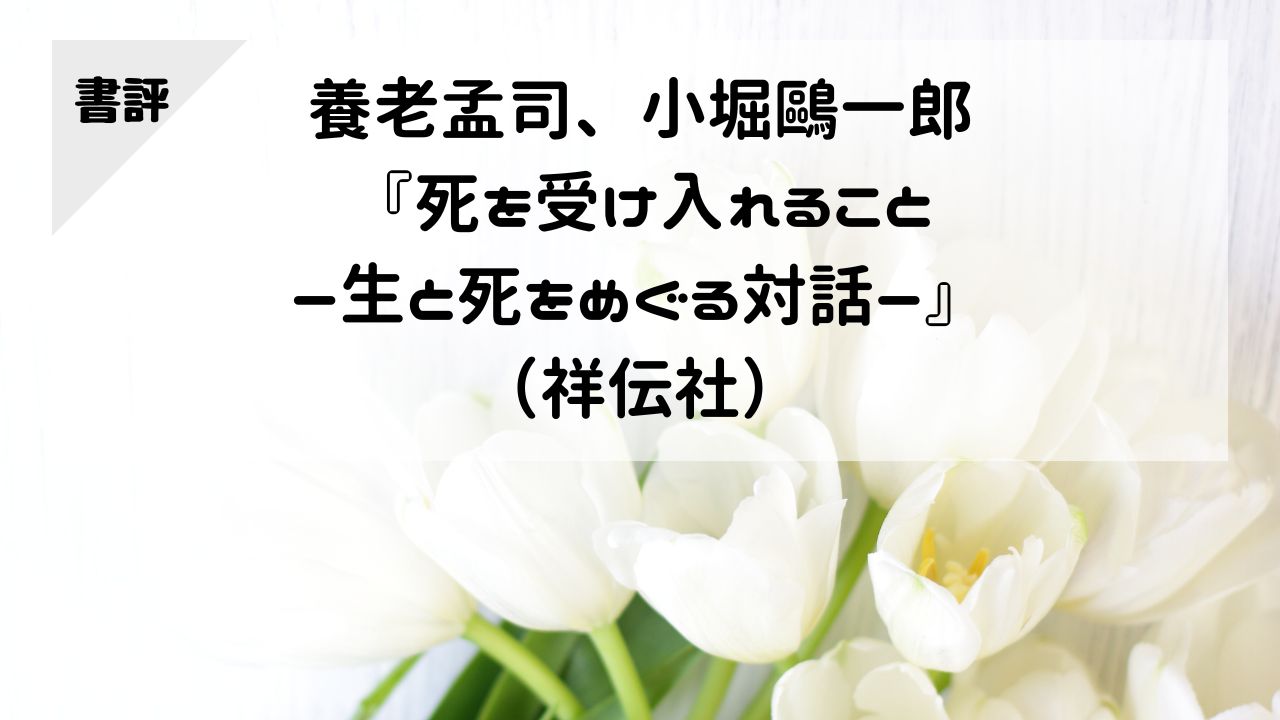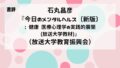身近な人の死に触れたとき、皆さんは何を思いますか?
私はここ2~3年のあいだに、知人やペットを含む家族の死が4回、新たな命の誕生が1回、訪れました。実は、それまでの人生ではほとんど生死の場面に出会うことがありませんでした。そのため、人の一生について考えたり、新たな命の将来に思いをはせたりと、死生観について深く考える時間が急激に増えていったのです。
「あの方の最期は幸せだっただろうか」
「この子は、この先どんな人生を歩むんだろう」
人生100年時代。いつまでも健康に生きていたいけれど、現在の科学技術では誰しも死を免れることはできません。幸福に生き、幸福に人生を全うする。そのヒントが載っているのが、今回ご紹介する『死を受け入れること』です。
本書は、大ベストセラーとなった『バカの壁』の著者でもある解剖学者の養老孟司氏と、映画『人生をしまう時間(とき)』が話題となった元外科医かつ現訪問診療医の小堀鷗一郎氏との対談です。
お二人とも東京大学医学部を卒業し、死と密接な関係がある仕事を長年続けてきました。年齢も近く出身校も同じですが、幼少期から現在に至るその経歴の違いは、それぞれの個性的な人生を象徴するかのようでした。
本書には、死にまつわる話から仕事内容の話、東大医学部の話など多様なテーマが収録されていました。本記事では、主に「死にまつわる話」を取り上げ、ご紹介していきます。
こんな方にオススメ
- 死ぬのが怖い
- 医療の世界で働きたい
- 家族の介護をしている
小堀鷗一郎氏と養老孟司氏の対話
さて、対談者の小堀氏と養老氏について、本書の帯にはこう書いてあります。
3000体の死体を観察してきた
解剖学者と
400人以上を看取ってきた
訪問診療医。
「養老孟司氏は知っているけれど、小堀鷗一郎氏の名前は初めて聞いた」という方も少なくないことでしょう。
小堀鷗一郎氏は、主に外科医として東京大学医学部附属病院と国立国際医療センター(現国立国際医療研究センター)で食道がん手術の専門医として定年退職まで勤めました。現在は、埼玉県新座市の堀ノ内病院にて訪問診療医として所属し、終末期の患者さんと関わる日々です。
執筆した書籍は養老孟司氏ほど多くありませんし、外科医として執刀を重ねてきたご経歴を踏まえると、なかなか一般人にはその名が知られていないのも納得ですよね。実は、小堀氏はあの森鷗外のお孫さん。鷗外の第3子、杏奴(あんぬ)氏のご子息です。
どうやって死なせようか
人びとがどこで死亡したかの統計があります。現代日本においては、死亡場所の8割以上が病院となっています。誰かを喪った経験がある方も、そうでない方も、この統計結果はさほど驚くものではないでしょう。病院だけでなく施設で亡くなる方もいますので、慣れ親しんだ自宅で生涯を終える方というのは近年だいたい1割程度と少なくなっています。
多くの人にとって、病院とは命を救うための場所でしょう。生を途絶えさせないために健康の維持増進を目指し、悪い病気を取り除いてくれる場です。しかし、死を迎える人びとの多くは、この病院で亡くなります。病院で生まれ、病院で死ぬ。現代の日本においては、そうした人生を歩む人が多数派なのだと思います。
訪問診療医として自宅で療養する患者の元を訪れる小堀氏は、以下のように語ります。
小堀 (中略)外科医の時は患者をどうやって生かそうかと考えていましたが、今は患者をどうやって死なせようかと考えるのが仕事です。最初は戸惑うところもありましたが、こういう医療をやって初めて医師としての職業を全うしたと言えると思っています。
引用元:養老孟司、小堀鷗一郎『死を受け入れること ー生と死をめぐる対話ー』(祥伝社)
養老 僕の母も兄も自宅で死にました。僕にとってはそれが当たり前です。
小堀 息子夫婦と五十年以上同居していた百五歳の女性から、「まだ続くでしょうか?」と聞かれたことがあったんです。「まだ続きます」と答えました。
僕が最初に行った時、息子はもう七十歳を過ぎていて、お嫁さんは能面のように無表情でした。どんなにうまくいっていても嫁姑が五十年以上一緒に暮らしていれば、そうなるのも仕方がない。家族にとってもう限界のように感じました。それで僕は、「あなたはそういうことがわかるただ一人の百歳以上の人です」と言ったんです。
その後、彼女は施設に入り、そこで亡くなりました。人生最後のソフトランディングを本人や家族とともにどうするかを考えるというのが今の仕事です。
在宅死する人びとは少ないということを理解しつつも、自宅で死にたいという方は多いでしょう。しかし、残される家族のことを考えると、そうも割り切れない部分がある。これと決まったマニュアルは存在しないし、患者とその家族の考えを尊重することの大切さと難しさを感じます。
この話を読んでいて、私は「看取り士」という仕事を思い出しました。この「看取り士」は、個人の人生の終わりに寄り添い、その生涯が閉じるまで一緒に過ごすというものです。
養成講座を受けることで資格取得できる仕事で、一般社団法人日本看取り士会が監修しています。
誕生の際は華やかに祝われます。しかし、死については特に身近な家族から忌避されることが多いことでしょう。本当は、死の際も誕生時と同じくらい重要な出来事として取り扱うというのが良いのかもしれません。
死は常に二人称で存在する
人はみな、自分が死んだという体験を誰かに共有することができません。養老孟司氏によれば、「死は常に二人称で存在する」とのこと。
養老 (中略)死は常に二人称として存在するんです。一人称の死というのは自分の死ですが、自分の死は見ることができませんから、存在しないのと同じです。その体験を語れる人はいません。
引用元:養老孟司、小堀鷗一郎『死を受け入れること ー生と死をめぐる対話ー』(祥伝社)
三人称の死は、自分とは関係のない人の死です。そういう三人称の死は、死体を「もの」として扱うことができます。死が自分に影響を与えるのは二人称の死だけです。
死の社会的な意味合いは大きい。だから要件を決めて判定しようとします。例えば、高齢の政治家が死んだと聞いても、もう死んでもいいよな、と思うのは、社会的意味合いとしてです。
時折、「老害」という言葉を耳にします。より過激な表現として「高齢者は早く死んだ方がいい」という言説も、特にコロナ禍以降、急速に広まったように思います。こうした暴論はいずれも「三人称の死」に基づくからか! と本書を読んでいて大いに刺激を受けた部分でした。
死は常に二人称で存在する。この対談は2020年2月から3月にかけて行われたとのことです。WHO(世界保健機関)のテドロス事務局長がスイス・ジュネーブの本部でパンデミック宣言をしたのが2020年3月11日。
その後、感染者数や死者数が具体的な数字で連日発表されていくようになっても、感染予防をしながらとはいえそれなりに日常生活を過ごしてきた私たちにとっては、コロナ禍は「三人称の死」の氾濫だったのかもしれません。
誰かの死を強く意識するのは、やはり「二人称の死」なのでしょう。
遺体が人に戻る
本書では、亡くなった方とどう向き合うかという話が随所にあるのですが、ここでは解剖時の遺体との向き合い方についての対話を紹介します。
養老 解剖をやっていると、亡くなった方も人だ、ということが通じないとよくわかります。死んだ人は特別だと思っているから、大事にしようとするとやたらと大事にしないといけないし、忌むべきものだとしたら、扱いがぞんざいになる。うんと持ち上げるか、うんと下げるかどちらかなんです。
引用元:養老孟司、小堀鷗一郎『死を受け入れること ー生と死をめぐる対話ー』(祥伝社)
僕は、口がきけない、動けない、そういう患者さんと同じ扱いをすればいいと思っています。患者さんが口をきけないからといって蹴っ飛ばしていいということはないでしょう? 僕はそこに差がないという意見です。(中略)
小堀 そういえば、養老先生は著書でこう書いておられましたね。
解剖学の教官になって、学生に解剖させる時に、四人で一体の解剖を何カ月もかけてやるのですが、たまたまある遺体のところに小さな花が生けてあった。「これは何だ」と尋ねたら、その四人の中の誰かが用意した、とそんなエピソードを書いていらっしゃいましたが、そういうことですね。
養老 そうです。そこで、遺体が人に戻るんです。
ご遺体のそばに花を生けるというエピソードは、私もよく覚えています。たしか『死の壁』という書籍に収録されていたかと思います。養老孟司氏の著書のうち、『バカの壁』『死の壁』『超バカの壁』の3冊は読んだのでそのいずれかだとは思います。なにぶん昔のことではっきりとは思い出せませんが。
この本に書かれていたエピソードは、その後、医学部に進学した高校時代の友人と久し振りに会って、互いが音信不通だった期間の出来事を話し合った際にも、似たような話を聞きました。きっと医学部の必修科目なのでしょう、その友人が解剖学の授業を受けた際も、お花が生けてあったということでした。
2024年末に、解剖実習の場でピースサインとともにSNSに写真をアップした医者が、大きな非難を浴びました。
この医者は「倫理観が欠如した投稿をしてしまった」と自らの行いを振り返っていますが、ご遺体と真摯に向き合うことができるか否かは、医師自身の死生観に委ねられているのかもしれません。
解剖学者は死者とのみ関わる仕事ではありますが、人を対象にする点では臨床医と同じです。ここ数年のあいだで他界した私の周囲の人びとのことを思い浮かべると、まだ私のこころの中に存在していることを実感します。
「二人称の死」は私のなかに生き続けている。身体は消滅しても、人は人ということなのかもしれません。
関連書籍
- 養老孟司『バカの壁』(新潮社):虫好きで有名な解剖学者といえば養老孟司氏。著書のなかで最も有名なのが『バカの壁』シリーズでしょう。平成で一番売れた新書だそうで、第1作のこちらは2003年のベストセラーになりました。
- 小堀鷗一郎『死を生きた人びと』(みすず書房):2019年、第67回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞。355人の看取りに関わった訪問診療医が語る、患者たちのさまざまな死が記録されています。
- 荒川龍『抱きしめて看取る理由 - 自宅での死を支える「看取り士」という仕事』(ワニブックス):終末期の方を見守る看取り士という仕事があります。子供の誕生は大きな喜びで迎えられるものの、愛する方の死というものは大きな悲哀であり、受け入れにくいもの。しかし、看取り士はこの一般常識を否定し、死の瞬間は「大切な締めくくり」として家族が感謝と共に身体を抱きしめて、笑顔で迎えることを促します。終末期の治療の在り方も議論の余地がありますが、「高齢者」ならぬ「幸齢者」の尊厳とはどうあるべきか?を考えさせられる本です。
- 和田秀樹『80歳の壁』(幻冬舎):80歳からの人生を楽しく過ごす秘訣を知る一冊。いま80代の方も、そうでない方にもオススメです。高齢の方が想定読者のため、文字も大きく読みやすいです。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- シェリー・ケーガン(著)、柴田裕之(翻訳)『「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義』(文響社):イェール大学での人気講義を書籍化。「死」についての哲学入門書です。死について論じた哲学者は数多く存在すると思うのですが、学生向けの講義を土台としているため本書はとりわけ読みやすいと思います。といっても、哲学なので何度も読み返す部分があることは覚悟した方が良いかと。本書は日本縮約版で、原著の形而上学的テーマが省かれています。どっぷり読みたい方は完全翻訳版をお読みになると良いです。
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪