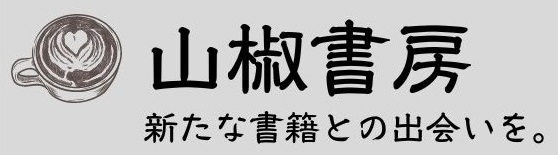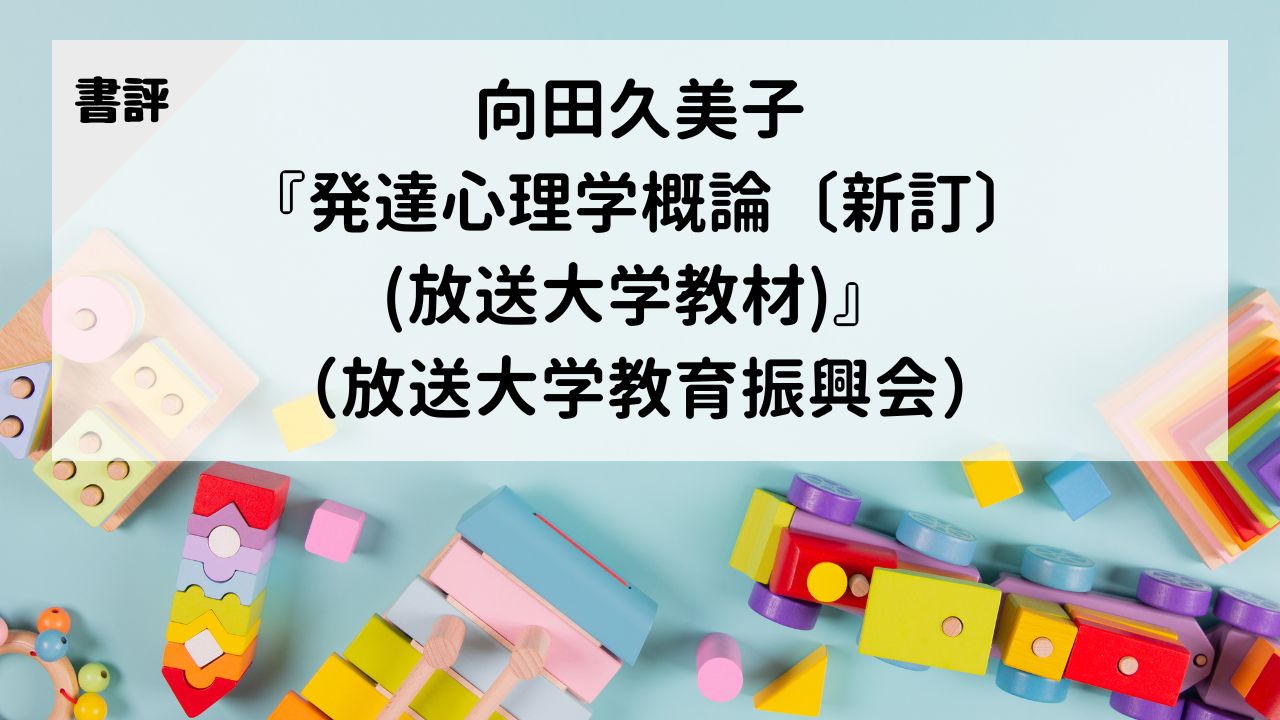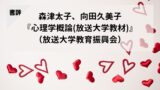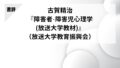少子高齢化という言葉を日常的に見聞きするようになって、随分と月日が流れました。気がつけば、少子高齢化の問題は日本だけでなく、先進国を中心に世界的に議論が交わされる重要なテーマになっていますよね。
昨年、新たな命が誕生して親族が増えた私。懐妊の知らせを受けてから、これからの子どもが歩む未来はどうなっていくのだろうか…と社会に対する関心が増していきました。必然的に、現世代が担うべき責任というものにも思いが至ることしばしば。
しかし、少子高齢化の影響もあってか、私は社会人になってから子どもという存在がとても遠い存在になってしまいました。「子どもと関わるうえで気を付けておきたい点があれば知りたいなぁ…」とか、「子どもの成長は早いというけれど、どのような発達過程を辿るのだろう?」と分からないことだらけ。
そこで、在学中の放送大学で気になっていた「発達心理学概論('17)」の科目を履修することにしました。かつて4年制大学で発達心理学を学んでいたとき、乳幼児の発達、特に「アタッチメント(愛着)」について講師が熱心に説明する姿が記憶に残っていたのです。子どものことを理解するなら発達心理学を学ぶのが良いだろう、と考えました。
ただ、4年制大学に通っていた当時は20歳前後で、自分が子どもを持つという姿もはっきり描けなかった私にとっては、勉強になるなぁと思いつつも、分かったような分からないような気持ちだけが残りました。それから15年以上ものあいだ親族内で子どもが誕生することもなく、やはり子どもという存在は私にとって馴染みの薄い存在であり続けました。
そして、「発達心理学概論('17)」で再び発達心理学を再び学び終えた私。あらためて感じたのは、発達心理学は子どもだけを対象にした学問ではないということです。「乳幼児が育っていく過程って面白いなぁ!」と感じたのは予想どおりでしたが、そもそも「発達」という言葉の深みをあらためて考えさせられたのでした。
今回は、子どもも高齢者も研究対象とする「発達心理学概論('17)」の印刷教材(テキスト)をご紹介します。
書籍は全国の書店などで購入できます。放送大学生でない方も、本科目の講義はBS放送などのテレビで視聴可能です。詳しい視聴方法は以下をご参照ください。
本講座の基本情報
本講座「発達心理学概論」は、放送大学で開講されている科目です。
- 2017年度開設
- 放送授業(ラジオ配信)
- 心理と教育コースの導入科目
具体的なシラバスはこちらからご参照ください。
放送授業はラジオで公開されており、書籍はAmazonほか各書店でお買い求めいただけます。各地域におけるテキスト取扱書店は下記をご参照ください。
こんな方にオススメ
- 子どもの支援に携わる仕事がしたい
- 子どもの成長や、高齢者の加齢に伴う変化に関心がある
- 生育環境が人生にどのような影響を与えるか知りたい
目次
本書の目次は下記のとおりです。全15回の放送授業に沿った章立てとなっております。
1 発達とは
2 発達心理学の諸理論
3 発達研究の方法
4 乳児期の発達:知覚とコミュニケーション
5 乳児期の発達:アタッチメントの形成
6 幼児期の発達:言葉と認知
7 幼児期の発達:自己と社会性
8 児童期の発達:認知発達と学校教育
9 児童期の発達:自己概念と社会性
10 青年期の発達:アイデンティティの形成
11 成人初期の発達:大人への移行
12 成人期の発達:中年期危機とジェネラティビティ
13 老年期の発達:喪失とサクセスフル・エイジング
14 発達と環境:メディアの影響
15 発達と環境:文化の影響
発達とは?
まずは、言葉の定義を確認しておきましょう。冒頭でも述べたとおり、発達心理学で取り扱う「発達」とは、子どもだけを対象にしたものではありません。
確かに、子ども時代の発達は目覚ましく、できないことができるようになったり、身体が大きくなったりと、獲得や増大といった上昇的変化に注目が集まりやすい。一方、成人期以降は体力が衰えたり、以前できたことができなくなったりと、喪失や減少といった下降的変化が意識される傾向にある。後者はかつて「老化」と一括りにされる傾向にあったが、現在では、上昇的変化も下降的変化も発達の一側面を表すものとみなされている。
引用元:向田久美子『発達心理学概論〔新訂〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
(中略)
このように、1960年代後半から、発達についての考え方は、徐々に「子どもが大人になるまで」から「受精から死に至るまで」に、また「上昇・増大・獲得」だけでなく「下降・減少・喪失」を含むものに変化していった。
とはいえ、「発達」という用語を聞いたとき、多くの人が子どもを思い浮かべるのではないでしょうか。たとえば、発達障害は一般的に幼児期や児童期に周囲に認識されることが多いだろうと考えられています。それゆえ、大人になってから発達障害と診断された場合は、わざわざ「大人の発達障害」という呼び方で区別しているのではと思います。
子ども以外も発達心理学の範疇に含まれるということは、要するに、子育てをしている方や子どもと関わる方以外にとっても役立つ学問だ、ということを意味します。
人間はみな誕生と共に老いていくことは避けられません。したがって、自分自身の今後の人生を考えるうえでも役立つ学問なのです。もちろん、老年世代の家族や仲間を持つ方にとっても、自分の言動を振り返る知見を得られるのが発達心理学です。
生理的早産という考え方
目次に示されているとおり、本書では人間の一生を乳児期、幼児期、児童期、青年期、成人初期、成人期、老年期の7段階に分けてその発達上の課題や知見を紹介しています。概論と名付けられただけあって、本書は専門的でありながら広範囲にわたる発達心理学の研究成果を分かりやすく解説しています。
なかでも、印象に残ったのは「生理的早産」という考え方。
(中略)この現象から、ポルトマンは、人間は進化の過程で大脳が肥大化し、二足歩行により産道が垂直化したため、妊娠期間が短くなり、早産(未熟な状態での出生)が常態化したと考えた。これを生理的早産と呼び、本来胎内で過ごすはずであった1年間を子宮外胎児期と名付けた。
引用元:向田久美子『発達心理学概論〔新訂〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
子宮外で胎児期を過ごすということは、種々の行動の発達が、多様な環境刺激との相互作用の中で、さまざまな方向に行動を発展させうることを意味している。こうした開かれた生得性こそが、人間の発達の特殊性である。また、成体に達するのに長い年月(約20年)がかかるのも、他の動物には見られない特徴であり、それだけ発達における環境の果たす役割が大きいと言えるだろう。
たしかに、野生の子鹿は生まれてすぐに自分の足で立てますし、犬も10ヶ月頃から出産可能です。動物によって寿命の長さが異なる点を勘案しても、人間の赤ちゃんが歩いたり話したりするのに約1年を要したり、出産可能となるまでに10年以上かかったりするのは、他の動物と比べてかなり未熟な期間が長いといえるでしょう。
さらに、成人とされる18歳や20歳を超えても「モラトリアム(アイデンティティを確立するための猶予期間)」の期間があり、将来の目標が見つからずに自分探しを続けている最中だという人々も少なくありません。早く産まれすぎてしまったため未熟な期間が長い、という考え方にはなるほどなと思いました。
環境も発達に影響を与える
さて、先ほど引用した「生理的早産」の説明では、こう書かれていましたね。
また、成体に達するのに長い年月(約20年)がかかるのも、他の動物には見られない特徴であり、それだけ発達における環境の果たす役割が大きいと言えるだろう。
引用元:向田久美子『発達心理学概論〔新訂〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
環境の果たす役割という観点では、本書の後半に位置する第14章と第15章が知見に溢れていました。第14章ではテレビ、ゲーム、SNSといったメディアの発達への影響を、第15章では生まれ育った地域の価値観が与える発達への影響が述べられています。
昨今、テレビで活躍していた有名人が週刊誌を含むメディアで問題点を指摘され、結果として露出が制限されたり引退するというケースがたびたび生じるようになりました。私は事実を深く理解しているわけではないので進退の是非や法的責任について論じるのは避けますが、気になるのは黄金時代の彼ら彼女らが築いてきたテレビ文化です。
メディアに関するこれまでの研究成果をまとめると、良質な内容を短時間利用することは発達に肯定的な影響をもたらすが、長時間に及ぶ利用や暴力的な内容への接触は否定的な影響をもたらすということである。
引用元:向田久美子『発達心理学概論〔新訂〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
私は、テレビ番組があることで日常に彩りが増え、時に笑い、時に涙する児童期・青年期を過ごしました。基本的には生活にプラスの効果があったと思います。学びもありましたし、友人との会話も弾みました。
しかし、時に侮蔑的な印象が含まれる表現が世間で日常的に使われている現状を考えると、テレビ番組の影響を考えずにはいられません。とはいえ、侮蔑を笑いや驚きといった形で包み込み、それが当たり前であるような見せ方は、世間に広く受け入れられていました。テレビの出演者と視聴者が一体となって作り上げたものだった文化だったのかもしれません。
こうした視聴経験は、自分を含めた同時代の人々の発達に影響を与えていたことだろうと思います。発達心理学の領域に、メディアとのつきあい方を考えさせられる内容が含まれるというのは、大きな収穫でした。
関連書籍
- 森津太子、向田久美子『心理学概論(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):心理学を学ぶ方は、まずこちらの書籍からスタートすると良いです。2024年度には改訂版が登場し、よりパワーアップしています。2018年度版について記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 小林真理子、塩崎尚美『乳幼児・児童の心理臨床(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):乳幼児と児童に特化した心理臨床を学びたい方は、こちらを是非。
- 大山泰宏『思春期・青年期の心理臨床〔新訂〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):思春期・青年期に特化した心理臨床を学びたい方は、こちらを是非。
- 宇都宮博、大川一郎『中高年の心理臨床〔新訂〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):中年期・老年期に特化した心理臨床を学びたい方は、こちらを是非。
- 米澤好史『やさしくわかる! 愛着障害―理解を深め、支援の基本を押さえる』(ほんの森出版):アタッチメント(愛着)の問題について基本から学びたいという方は、こちらのような入門書から紐解いてみるのがよいでしょう。
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪