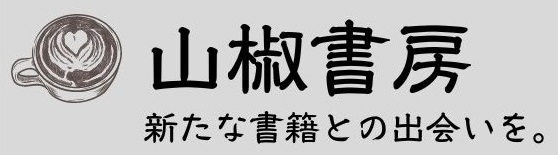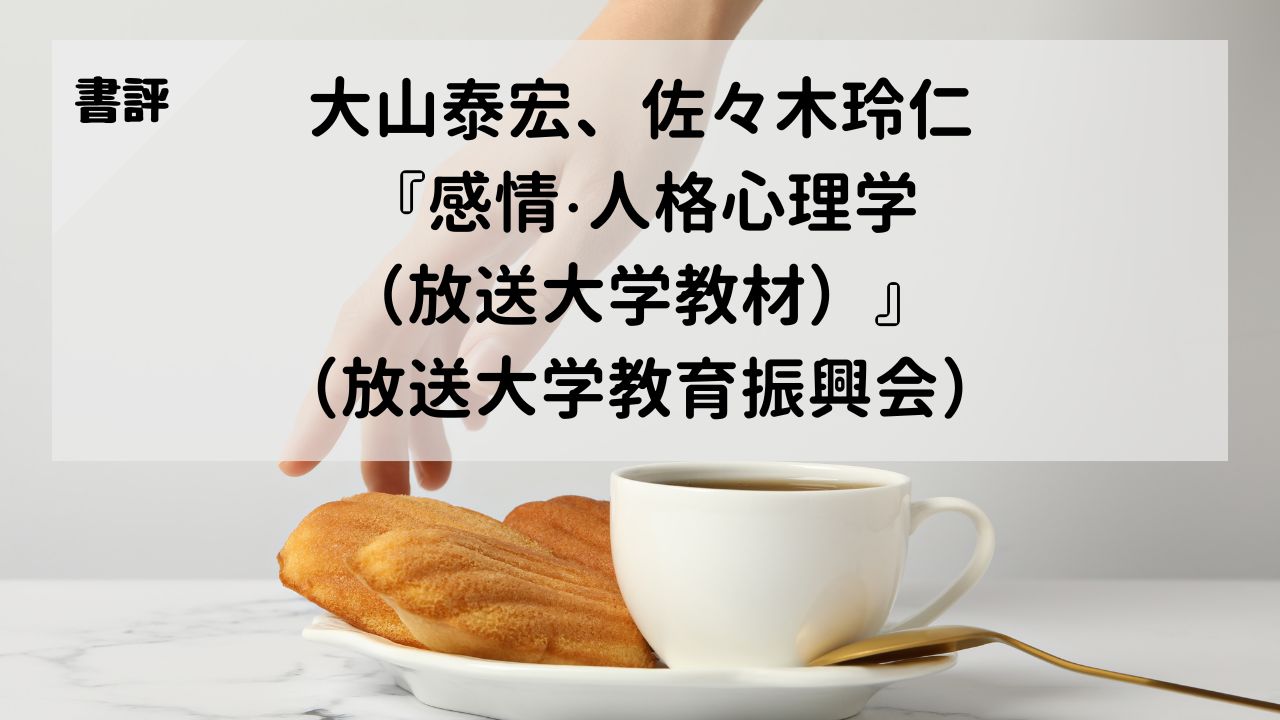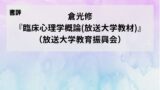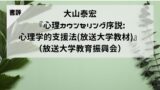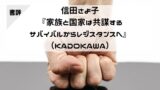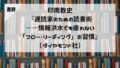放送大学で学び始めて3年目。印刷教材(テキスト)を読みながら講義を聞き学びを深めていく半年間は、忙しいながらも充実感を与えてくれています。学べば学ぶほど新たな知見が積みあがっていく、それは、前進している実感が得られるということなのです。
ところが、今回ご紹介する科目はこれまでの科目と少し毛色が違いまして。というのも、学べば学ぶほど分からないということが分かっていくという科目なのです…!
こうした「分からなさ」は私の理解不足によって生じているのではなく、また講師のスキル不足によって生じているのでもありませんでした。「感情・人格心理学」という科目は、感情や人格というものの定義や測定にあたっては考慮すべき点がたくさんあり、一筋縄ではいかないということに気づかされる学問なのです。
公認心理師をはじめとして、対人支援に関わる職種は人間を相手にしています。となると、もちろん激しい感情に触れたり、人柄について考える機会は比較的多いことでしょう。講師の大山泰宏先生、佐々木玲仁先生のお二人とも心理臨床の専門家です。そうしたキャリアを持つ講師陣が感情・人格の捉えにくさを語るからこそ、より説得力を持って読み進めることができました。
印刷教材(テキスト)は、「講師が一方的に知見を授ける」というよりは「講師と学生が一緒に議論を深めていく」というスタイルに近いです。学生が読みながら主体的に考えていく姿勢を大切にすることで、得るものが多いことでしょう。
今回は、分かっているようで分かっていない感情や人格について考えてゆく「感情・人格心理学」の印刷教材(テキスト)をご紹介します。
書籍は全国の書店などで購入できます。放送大学生でない方も、本科目の講義はBS放送などのテレビで視聴可能です。詳しい視聴方法は以下をご参照ください。
放送大学科目の書評記事のまとめはこちら
放送大学の科目についての書評記事は以下にまとめました! ご興味あればご参照ください♪
本講座の基本情報
本講座「感情・人格心理学」は、放送大学で開講されている科目です。
- 2021年度開設
- 放送授業(ラジオ配信)
- 心理と教育コースの専門科目
具体的なシラバスはこちらからご参照ください。
放送授業はラジオで公開されており、書籍はAmazonほか各書店でお買い求めいただけます。各地域におけるテキスト取扱書店は下記をご参照ください。
こんな方にオススメ
- 公認心理師を目指している
- 対人支援に関わる仕事がしたい
- 感情や人格について考えを深めていきたい
目次
本書の目次は下記のとおりです。全15回の放送授業に沿った章立てとなっております。
1 感情と人格ーー講義を始めるにあたって
2 感情はなぜあるのか
3 感情を表すーー表情のはなし
4 感情の発達
5 感情と記憶
6 感情の生理的基盤
7 感情の障害
8 感情の測定
9 人格の概念
10 人格の記述ーー類型論と特性論
11 人格の測定
12 人格の発達
13 人格と環境ーー文化と状況
14 人格と心理療法
15 感情・人格と日常
読み物としても楽しめる
第1章の第4節「本書の着地点」では、以下のように述べられています。
本書ではさまざまな側面から感情と人格について論じてきた。ここに紹介したものは、第1節で述べたように、理論のための理論でなく、また研究者コミュニティで閉じられている議論に終わらせないためにも、これらの内容を統合しつつ、日常生活における「気持ち」と「人がら」につながる論点が必要であろう。既に論じてきたように、この2つのテーマについて論じ得る内容は数多い。しかし、これらの論からどのようなことが引き出し得るかについて述べることは、これらのテーマが日常生活について直結するという特性上、どうしても必要なことであると筆者は考えている。具体的にどのような着地になるのか、それが航空機のような滑らかな着地になるのか、パラシュートを使った半ば強引な着地になるのかについては、本章も含めた第14章までを経てからゆっくりと考えることとしたい。
引用元:大山泰宏、佐々木玲仁『感情・人格心理学(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
この文章を読んで分かるように、本書は「教科書」というよりは一般的な「読み物」として読める体裁の書籍となっています。この第1章を受けてまとめられた第15章での着地が、「航空機のような滑らかな着地」だったのか「パラシュートを使った半ば強引な着地」であったかは、実際に手に取ってご確認ください!
そして、「日常生活に直結する」という点が重視されていることは、本書を読んでいるとよく伝わってきます。人を相手にする心理臨床の専門家だからなのか、その学びには「手触り感」のようなものが感じられました。アカデミックの世界を踏まえつつも、より実生活における援用が意識されているということです。文章は理詰めで哲学的に論じられてゆきます。
文学や演劇からの考察も
本書では、小説やエッセイからの引用がなされる場面があります。たとえば、第5章「感情と記憶」では次のとおり。
思い出そうとしなくても思い出してしまう記憶の想起は、無意図的想起と呼ばれている。プルーストの小説『失われた時を求めて』の冒頭では、紅茶に浸したマドレーヌの味と香りから、何かの記憶が「私」の中で強い感情を伴って強烈にうごめき始め、それがエピソード記憶として想起されるまでにしばらく時間が必要であった。また、村上春樹の小説では、飛行機が空港に着陸して、天井のスピーカーから小さな音で、ビートルズの『ノルウェイの森』が流れだしたときに、「僕」は激しく混乱し動揺し、一挙に20年前の出来事を思い出す。記憶の無意図的想起は、意図的な制御を利かせることができる意図的想起よりも、想起時に体験される感情が強いという(山本、2018)。
引用元:大山泰宏、佐々木玲仁『感情・人格心理学(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
『失われた時を求めて』も『ノルウェイの森』も超有名な作品ですので、内容をよく知っているという方も多いことでしょう。実は私はどちらも未読だったのですが、『失われた時を求めて』での「紅茶に浸したマドレーヌ」が小説のなかで極めて重要な役割を果たすということは存じておりました。思い出そうとしなくても思い出してしまう記憶(無意図的想起)の例としては、大変わかりやすいですよね。どちらも読了済みの方ならなおさらそう思うことでしょう。
ほかにも、平田オリザ氏の演技論からの引用もありました。以前、信田さよ子氏の『家族と国家は共謀する』を読んだ際、映画作品を引き合いに出して論じている部分がたくさんありました。人間理解には、映画・文学・演劇といった芸術作品が貴重な知見をもたらすということがよく分かります。
分からないということに気づいていく
本記事の冒頭で、私は「感情・人格心理学」という学問について以下のように書きました。
「感情・人格心理学」という科目は、感情や人格というものの定義や測定にあたっては考慮すべき点がたくさんあり、一筋縄ではいかないということに気づかされる学問
その一例として、人格の測定と記述に関する部分を引用します。
人格をどのようなものとして捉えるにせよ、手にとって見ることのできないこの概念について実際にあれこれと論じるためには、何かしらの方法で人格を測ること(測定)と、それらを言語化して述べること(記述)が必要である。もし人格が実体であるならば、測定が正確に行われている範囲であればどの方法をとっても同じ結果が出てくるはずである。しかし、実際は多くの場合そうはならない。
引用元:大山泰宏、佐々木玲仁『感情・人格心理学(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
これは、「測定が正確でない」可能性と、「測定自体は正確でも方法によって人格が変化してしまう」可能性の両方がある。また、記述はより複雑で、同じ測定の結果があったとしても記述の仕方(言語化の方法)によって読み手に伝わる人格は異なったものになる。人格のこの不定性は、本当は安定しているはずのものが正確に読み取れなかったために生じている誤差なのか、それとも本来不定であるものを正確に表現しているのかを判定することは簡単ではない。
いかがでしょうか? 突き詰めて考えていけばいくほど、一筋縄ではいかないということがよく分かるのではないでしょうか。こうした分からなさと深く向き合い続ける忍耐さが、人と向き合う心理臨床には必要とされるのだろうな、とも感じました。
臨床に関心がある方は、是非一読してみてください。
関連書籍
- 森田美弥子、永田雅子『心理的アセスメント(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):人の感情や人格を捉える方法としてアセスメントを学ぶならこちらを是非。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 倉光修『臨床心理学概論(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):臨床心理を学ぶ方は、こちらを是非一読ください。臨床心理学の基礎が学べます。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 大山泰宏『心理カウンセリング序説: 心理学的支援法(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):カウンセリングや心理療法をさらに深く学びたいという方にはこちらがオススメです。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 信田さよ子『家族と国家は共謀する サバイバルからレジスタンスへ』(KADOKAWA)アダルトチルドレンブームの火付け役の一人となった臨床心理の専門家です。現在は日本公認心理師協会の会長です。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪