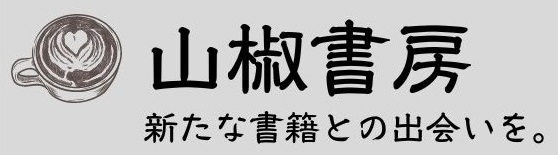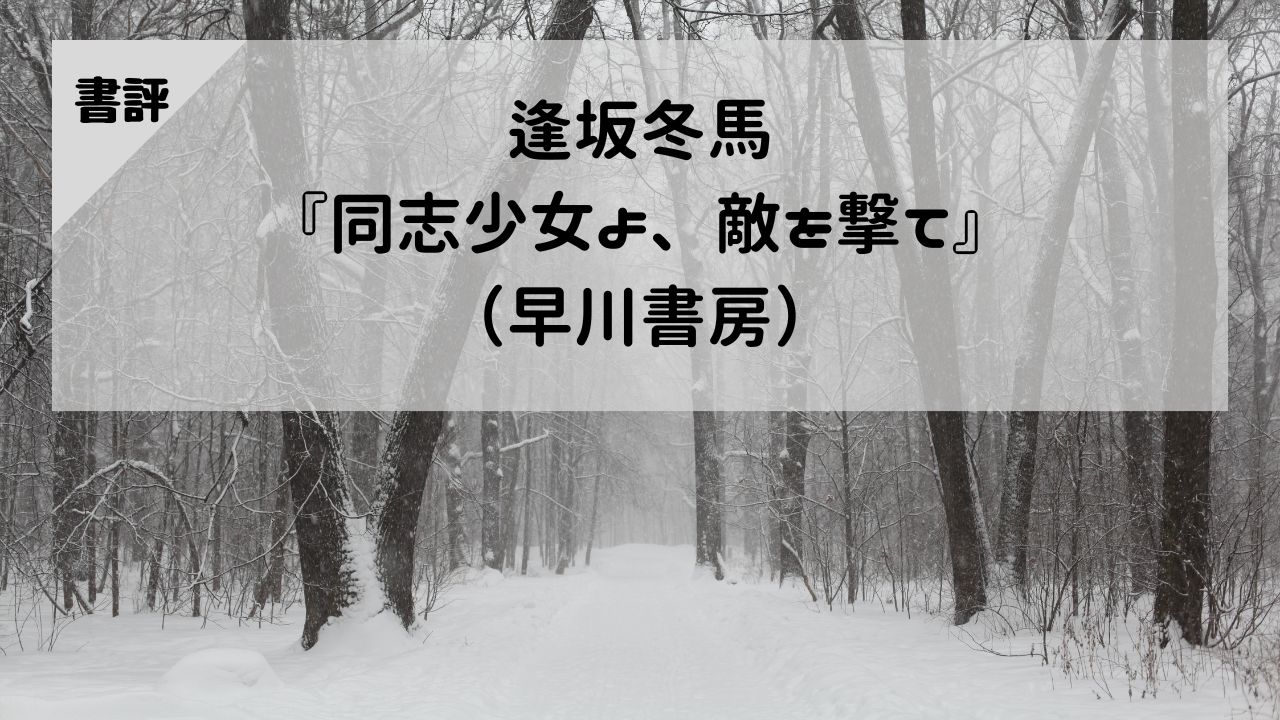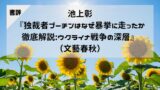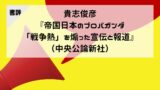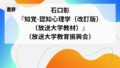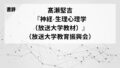今回ご紹介する一冊は、第11回アガサ・クリスティー賞大賞、2022年本屋大賞を受賞した逢坂冬馬氏の『同志少女よ、敵を撃て』です。
巻末に付されたアガサ・クリスティー賞での選評を見るに、かなりの高評価! 北上次郎氏によれば、「選考委員が全員最高点を付けたのは、アガサ・クリスティー賞史上初めてである」とのこと。なんと…! 素晴らしいですね!! 実際、スケールといい作品の持つ深みといいすごい小説でした。
ロシアがウクライナへの侵攻を開始してから、さらなる注目を浴びた本作。さっそく見ていきましょう!
こんな方にオススメ
- 戦争中に女性がどう生き抜いたか知りたい
- ロシア視点での戦争の歴史を学びたい
- 史実を元にした良質なミステリー小説が読みたい
あらすじ
出版元の早川書房での紹介文を引用させていただきます。
独ソ戦が激化する1942年、モスクワ近郊の農村に暮らす少女セラフィマの日常は、突如として奪われた。急襲したドイツ軍によって、母親のエカチェリーナほか村人たちが惨殺されたのだ。自らも射殺される寸前、セラフィマは赤軍の女性兵士イリーナに救われる。「戦いたいか、死にたいか」――そう問われた彼女は、イリーナが教官を務める訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意する。母を撃ったドイツ人狙撃手と、母の遺体を焼き払ったイリーナに復讐するために。同じ境遇で家族を喪い、戦うことを選んだ女性狙撃兵たちとともに訓練を重ねたセラフィマは、やがて独ソ戦の決定的な転換点となるスターリングラードの前線へと向かう。おびただしい死の果てに、彼女が目にした“真の敵"とは?
本書を読む醍醐味
まず本書について語る前に、ロシア文学研究者の沼野恭子氏が寄せた「推薦のことば」の一部をご紹介しましょう。本書を読む醍醐味を簡潔に説明するならば、これ以上に洗練された言葉はないと思ったからです。
逢坂冬馬の『同志少女よ、敵を撃て』は、第二次世界大戦時、最前線の極限状態に抛りこまれたソ連の女性狙撃手セラフィマの怒り、逡巡、悲しみ、慟哭、愛が手に取るように描かれ、戦争のリアルを戦慄とともに感じさせる傑作である(当時、実際に女性狙撃手がいたのだ)。読者は、仇をとることの意義を考えさせられ、戦争の理不尽さを思い知らされ、喪失感と絶望に襲われながらも、セラフィマとともに血なまぐさい戦場を駆け抜けることになるにちがいない。
引用元:逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』(早川書房)
そう、本作は主にセラフィマという少女の視点から、その感情の変化と戦争の理不尽さに身を震わせてしまう作品。突如として奪われた平穏な日常から復讐の鬼となり、狙撃兵として仲間たちと過酷な訓練に耐える姿は、少女の成長物語として読むこともできました。
あどけなさを残した少女たちの姿を眺めながら思い出したのは、深緑野分氏の『ベルリンは晴れているか』。こちらの作品では終戦直後のドイツを舞台に物語が進みますが、少女が主人公であたたかみのある文章表現は雰囲気が少し似ているなと感じました。
しかし、そんな成長物語がゆるゆると続くわけでもなく、ついに激戦地のスターリングラードへ。いきなり実戦の場で訓練の成果を発揮する機会が訪れるのです。この瞬間から、戦争の過酷さ、冷酷さ、理不尽さに直面し、読者は打ちのめされることでしょう。
本作の最も素晴らしいところは、実在した女性狙撃兵を主役に置き、その視点から戦場を眺め心情を吐露させることで、数字のみで語られがちな歴史にかなりのリアリティを与えている点でしょう。
戦争における女性の生き方
全編をとおして感じたのは、本作では戦時中におけるすべての女性の生き方に光を与えている点です。狙撃兵として敵を撃つ女性、看護師として部隊をサポートする女性、敵国の兵士と通じる占領地の女性、パルチザンの女性、敵国の女性、子どもを守る女性。
「どの生き方が正解か」といった見方ではなく、さまざまな事情を含めてそのような生き方があった、そう生きざるを得なかった、という理不尽さが描かれているのがよかったです。理不尽さがありながらも、生き抜いていくしたたかさの描写は、希望も感じさせました。
一つの視点として、女性狙撃兵の生き方を考えてみます。旧ソ連で実際に女性が一流の狙撃兵として活躍していたことは、リュドミラ・パヴリチェンコなど実在の狙撃兵をとおしてよく知られていますが、これは当時の諸外国を眺めてみても極めて異例だったといえるでしょう。戦時中、日本の女性が実践的な戦闘技術を学び前線で活躍していた(慰安婦を除く)、という話は私はあまり聞いたことがありません。
女性狙撃兵であるセラフィマや仲間たちは、兵士としての自分、女性としての自分、狙撃を繰り返し戦果をあげる自分、それらすべての事実に葛藤を抱きながら一流の狙撃兵として成長していきます。あどけなかった少女が、読んでいて悲しくなるくらいに優秀な狙撃手として成長していきます。
その活躍について、味方である隊内部からは感謝や畏敬の念を抱かれながらも、セラフィマを含む女性狙撃兵は、あからさまな侮蔑を向けられることが珍しくなかったようです。
だがときおり女故に絡んでくる連中がいるのが目障りだった。
引用元:逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』(早川書房)
狙撃小隊の面々の切り替えは早かったが、見知らぬ歩兵たちはそうでもなかった。
「あんなのが自分の女だったらどうするよ。殺しまくりの女房だぞ」
「女? あれが女に見えるのか? 目の錯覚だろう」
「敵」とはいったい誰なのか?
ソ連は、多大な犠牲を払いながらもナチス・ドイツに大打撃を与えました。スターリングラードの戦いがまさにそうですし、アウシュヴィッツ強制収容所の解放もソ連により行われました。
2022年に起きたロシアのウクライナ侵攻では、プーチン大統領が「ナチスからウクライナを解放する」というような発言をしていました。それほどまでに、第二次世界大戦におけるソ連の活躍は現ロシア国民にとって重要な史実であるといえるでしょう。
プーチン大統領は今回の戦いはウクライナのネオナチとの戦いだと正当化しています。ロシアとウクライナは同じナロードであると強調しながらも、「多くの人がナチスの民族主義のプロパガンダに洗脳されている」と述べています。
引用元:「【詳しく】プーチン大統領の“誤算” 予兆はいつから?分析」(NHK NEWS WEB、2022年4月5日 17時18分)
本書では、ウクライナ出身の女性狙撃兵オリガが登場します。オリガは本作のトリックスターと見ることも可能です。オリガが狙撃小隊のなかでどのように振る舞うかという点は、考察に値します。
物語の後半では、綿密に計算された軍事行動や、敵国兵士との探り合いにハラハラしっぱなしでした。ここに良質なミステリーとしての特徴をみることができます。そして、結末に近づいた頃、小説タイトルがそのまま登場する部分があります。
同志少女よ、敵を撃て。
引用元:逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』(早川書房)
この瞬間、セラフィマだけでなく読み手の頭のなかも研ぎ澄まされ、静寂が訪れることでしょう。「敵」は、ドイツなのか。それとも、兵士か。狙撃兵か。母を射殺した仇なのか。読みながら、「あぁ…」とつい声を漏らしてしまうその最後に、是非注目していただきたいです。
関連書籍
- スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ(著)、三浦みどり(訳)『戦争は女の顔をしていない』(岩波書店):500人以上の従軍女性から聞き取りをおこない戦争の真実を明らかにした、ノーベル文学賞作家の主著。戦争というものはとかく男性目線で語られがちであり、女性目線でのまとまった記録はなかなかありません。そういった意味で非常に価値がある一冊です。
- 深緑野分『ベルリンは晴れているか』(筑摩書房):第160回直木賞の候補作として選出され、2019年本屋大賞第3位、第9回Twitter文学賞(国内編)第1位を受賞。ナチス・ドイツが敗れ米ソ英仏に統治されていた時期のベルリンで、ある事件が起きて――。こちらはドイツの少女目線で物語が展開されます。『同志少女よ、敵を撃て』を読んでいるあいだに特に思い出された作品でした。
- 大木毅『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』(岩波書店):2020年新書大賞を受賞した本書。極めて苛烈な戦いとなった独ソ戦は、ウクライナ侵攻からも分かるように、他国間関係や人々への価値観に未だに影響を及ぼしています。
- 池上彰『独裁者プーチンはなぜ暴挙に走ったか 徹底解説:ウクライナ戦争の深層』(文藝春秋):ロシアとウクライナの歴史を学ぶならこの一冊から。中国共産党についての話題も勉強になります。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- ミハイル・シーシキンほか(著)、沼野充義・沼野恭子(編訳)『ヌマヌマ ; はまったら抜けだせない現代ロシア小説傑作選』(河出書房新社):本記事の冒頭で引用した「推薦のことば」の沼野恭子氏と沼野充義氏は、ロシア文学者の素敵なご夫婦です。そんなお二人が編んだ現代ロシア小説の傑作アンソロジー。ちなみに、お二人とも放送大学で授業を持っています(2025年8月現在)。放送大学の学生さんでロシアにご興味がある方は、探してみてください!
- 奈倉有里『夕暮れに夜明けの歌を 文学を探しにロシアに行く』(イースト・プレス):『同志少女よ、敵を撃て』を著した逢坂冬馬氏の実姉は、ロシア文学者の奈倉有里氏です。こちらの書籍は第32回紫式部文学賞を受賞。すごいご姉弟ですね!
- ノーマン・オーラー『ヒトラーとドラッグ 第三帝国における薬物依存』(白水社):ドイツ・ロシア両国家ともに、ナチス・ドイツについての言及は多々なされています。こちらはナチス・ドイツによる覚醒剤利用との関連も含めて深みのある一冊。一般市民にもメタンフェタミンが広く利用されていました。
- 貴志俊彦『帝国日本のプロパガンダ-「戦争熱」を煽った宣伝と報道』(中央公論新社):日本の戦争を振り返る一冊としては、こちらをオススメします。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪