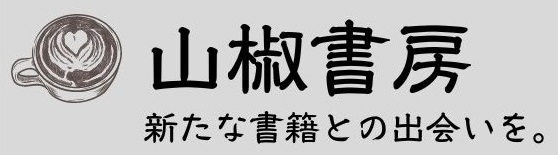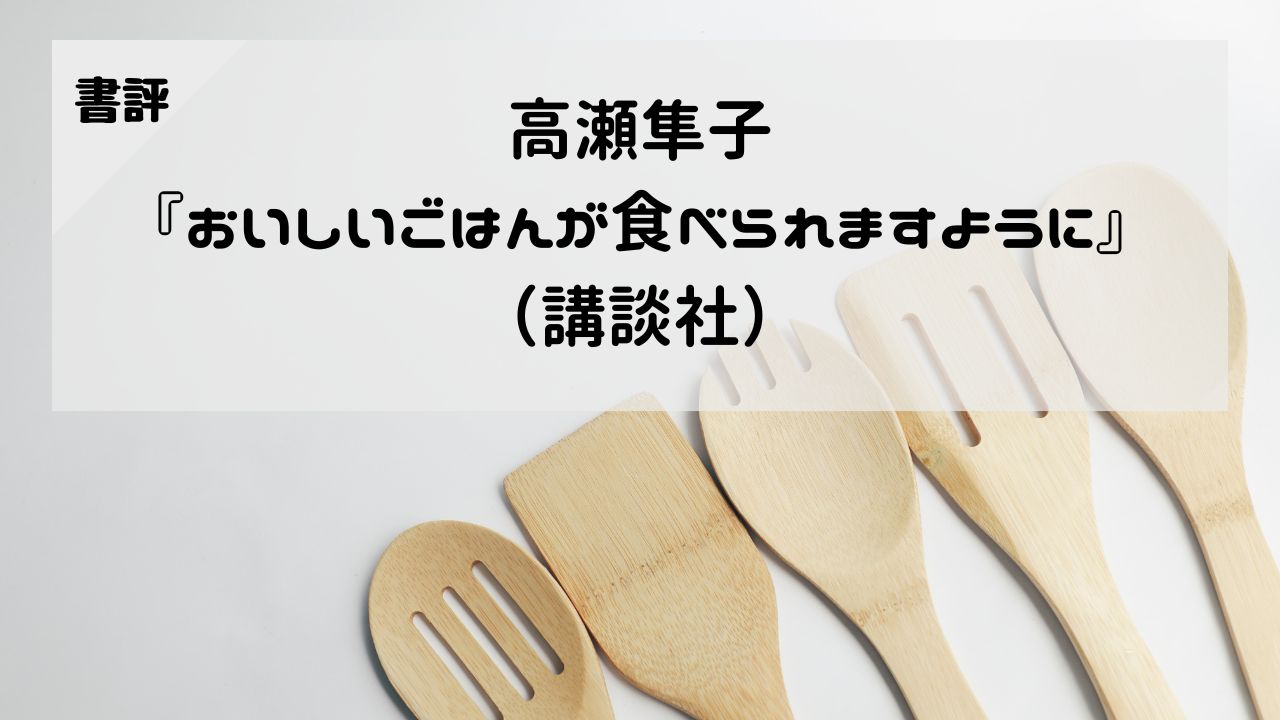今回ご紹介するのは高瀬隼子氏の『おいしいごはんが食べられますように』。第167回芥川賞受賞作品です!
高瀬隼子氏の作品を読んだのは今回が初めてだったのですが、実は日本経済新聞の木曜連載コラム『プロムナード』で高瀬氏のエッセイを拝読していた私。高瀬氏の柔らかい文章に惹かれ、毎週楽しみに拝読していたのでした。
この連載コラムのなかで特に興味を惹かれたのが、本作『おいしいごはんが食べられますように』のタイトル決めに悩んだというエピソード。120個ものタイトル案から選ばれた作品名が、『おいしいごはんが食べられますように』だというのです。
芥川賞を受賞した『おいしいごはんが食べられますように』というタイトルの小説がある。ごはんが大好きな人と、そんなに好きではない人が出てくる小説なのだけれど、これもタイトルには困った。今、このエッセイを書きながら過去の作業フォルダを開いて数えてみたら、タイトル案が120個もあって、驚いた。(50個くらいだったかな、と記憶していた)いくらなんでも迷いすぎだ。
引用元:タイトル 小説家・高瀬隼子(日本経済新聞、2023年5月15日 14:00 [会員限定記事])
そして、この『おいしいごはんが食べられますように』はいい意味で想像を裏切る作品…!これから読む方にまずお伝えしておきたいのは、タイトルから想像されるような癒し系たべもの小説では決してないということです。
常に漂う不穏な空気、登場人物たちのなかに浮かぶ暗い感情、確実に存在する理不尽…。読んでいて身につまさせるような気分になってしまう方もいることでしょう。日頃、誰もが感じているモヤモヤをキレイゴトとして隠すことはせず、本音と建前を使い分けながら生きていく登場人物たちについて、その感情を丁寧に描写している作品です。
さっそく見ていきましょう!
こんな方にオススメ
- お仕事小説が読みたい
- 職場の人間関係に悩んでいる
- 感情描写が丁寧な作品を探している
本書の主な登場人物
二谷
職場でそこそこうまくやっている。今の職場は、3ヶ月前に転勤してきたばかり。
ちゃんとしたごはんを食べるのは自分を大切にすることだって、カップ麺や出来合いの惣菜しか食べないのは自分を虐待するようなことだって言われても、働いて、残業して、二十二時の閉店間際にスーパーに寄って、それから飯を作って食べることが、ほんとうに自分を大切にするってことか。(後略)
引用元:高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』(講談社)
芦川
皆が守りたくなる存在で料理上手。仕事のミスが多く、体調不良でたびたび休む。
芦川さんが差し出しているのはマフィンだった。
引用元:高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』(講談社)
「昨日はすみませんでした。時々、頭痛薬を飲んでも治まらないくらい、頭が痛い時があって。帰って、もう一回薬を飲んで寝たら治ったので、作ったんですよ。よかったら召し上がってください。仕事、代わっていただいて、ありがとうございました」
押尾
仕事ができてがんばり屋。入社してから4年間、1年先輩の芦川さんと同じ職場で働く。芦川のことが苦手。
「さっきの、二谷さんが言ってた芦川さんは予定外のことが苦手ってやつ、多分そのとおりなんだろうなって思うんですけど、別に芦川さんがそう言ってるわけじゃないじゃないですか。わたしはこれが苦手でできませんって表明してるわけじゃない。でも支店長や藤さんや他のみんなも、うちの支店に来てまだ三か月しか経ってない二谷さんでも、分かってるでしょう。それで、配慮してる。それがすっごい、腹立たしいんですよね」
引用元:高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』(講談社)
芦川さんという存在
本作は、二谷と押尾との視点で交互に物語が進んでいきます。しかし、物語の中心を貫くキーパーソンは常に芦川です。
芦川さんは、いつも弱い。誰かが守ってあげなければならない。支店長を含めた職場全体でこのような構造ができあがっており、難しい案件で職場全体が忙しくなり業務量が増えた場合でも、芦川さんだけは早めに帰宅することが暗黙のうちに許されます。そして、遅くまで残ることができないというお詫びに、お菓子を職場のみんなに配ります。
皆さんの職場にこうした芦川さんのような方はいらっしゃいますか。
時代や職場によりいろいろではありますが、程度の差はあれこうした状況はよく見られる光景ではないかと思います。
「これは男の俺がやるべき。女性にこういう仕事はさせられないから」
「病み上がりだからしょうがないよ、無理しないでね!」
「時短勤務の人のことも考えて、仕事量の調整が必要だね」
「いつもご迷惑をかけてすみません。もしよかったら、お詫びにこのお菓子、どうぞ。これからも宜しくお願いします」
自分自身のなかに芦川がいるし、二谷も押尾もいる。そんな風に感じました。そして、周囲からみて弱い方が強い方に勝つという構図ができあがっていきます。
自分の人生を主体的に生きているか
本作を読んで芦川という存在に嫌悪感を抱く人もいるでしょうし、自分を見ているようだと身につまされる方もいるでしょう。本作では芦川視点での心情描写がないので、芦川本人の心のうちは読み手の想像に委ねられています。
ただ、芦川という人物を、善か悪かの物差しで語るのはおそらく適切ではないだろうというのが私が抱いた感想でした。というのも、この芦川という人物が最も自分自身の人生を主体的に生きているように見えたからです。
「今日は、これです」
引用元:高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』(講談社)
芦川さんが笑顔で差し出しているのは、黄色い桃のタルトだった。うすい水色の懐紙に載せられている。平日の夜にこんなのを作る時間があるのか。とっさに、まず、それが頭に浮かぶ。
一方で、押尾はそうではありません。高校生のときに3年間やっていたチアリーディングについては、次のように語ります。
「わたし別にチアが好きなわけじゃなくて、真面目で、できちゃったからしてただけなんですよね。高校の、三年の夏手前までだから、本格的に活動してたのは二年間。高校のクラスに同じ中学からの子が少なくて、最初に隣の席になった子がチアの体験入部するっていうから付いて行って、そのまま一緒に入部することになって、練習はきつかったけど、運動部の練習なんかどこもそれなりにきついじゃないですか。めっちゃ嫌ってこともなくて、単に引退まで続けた。(後略)
引用元:高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』(講談社)
人生における優先順位は人それぞれ違います。誰がその優先順位を決めるのか、という観点でみた場合に、芦川が最も主体的に生きているように見えるのです。
きちんとした食事をとらなければならないのか
食べものという観点でいえば、二谷と芦川の考え方が対局にあります。「きちんとした食事をとるべきだ」という芦川の言い分は正しい一方で、二谷にとっては暴力的なことばとして捉えられます。
(中略)この人に、ぐつぐつ煮えていく鍋を見つめている間、おれはどんどんどんどんすり減っていく感じがしますよ、と言っても伝わらないんだろうと思うと、顎に力が入らなくなる。咀嚼するのが面倒くさい。芦川さんみたいな人たちは、手軽に簡単、時短レシピ、という言葉を並べながら、でも、食に向き合う時間は強要してくる。
引用元:高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』(講談社)
おそらくどちらの主張も正しいのでしょう。私の実体験としては、二谷に共感してしまうところです。
まだ働き方改革も進んでいなかった時代、自分も含めて大学の同窓生には終電までに帰宅できない人も少なくありませんでした。ある友人は、23時に会社を出て帰宅したあと、そこから自炊を始めるのだと言っていました。「白菜はこうすると長持ちするんだって」と微笑みながら。野菜を売っているスーパーはすでに閉店しているからです。
自分には、夜遅く帰宅してから自炊するという生活はできませんでした。かといって毎日惣菜を購入すると食費にも響きますし、週末に料理の作り置きをしてしのぐ日々。
だからこそ思うのです。栄養バランスに配慮されたきちんとした食事、規則正しい起床・就寝をルーティン化できる状態というのは、日常の予定外のタスクが免除されているか、そもそも少ない状況なのではないかと。
こういう状況を享受している人を非難したいわけではありません。状況に応じて、それまで維持できていた「きちんとした生活」を諦めた方が、日常生活の満足度があがる可能性があるということなのでしょう。
関連書籍
- 土井善晴『一汁一菜でよいという提案』(グラフィック社):たべものを巡る文章が読みたい方はこちらを是非。「料理がんばろ!」と思うものの挫折してしまうのは、自分で勝手にハードルを上げてしまうため。プロの料理人じゃないなら、気張らずに取り組んでみれば良いのです。まずは一汁一菜から、という土井さんの言葉に救われる一冊。新生活を迎える方に読んでもらいたい本です。
- 柚木麻子『BUTTER』(新潮社):おいしい食べ物がたくさん登場する、第157回直木賞候補作です。木嶋佳苗事件を題材にした長編小説なのですが、作品の本質は現代の生き辛さに焦点を当てています。物語が進むとともに自分の価値観が揺さぶられ、読んだ後はなんだか開放感で一杯です。
- 小川糸『ライオンのおやつ』(ポプラ社):おいしい食べ物がたくさん登場する号泣作品。読むだけでおいしい作品なのだけれど、とにかく涙が止まりません。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 瀬尾まいこ『そして、バトンは渡された』(文藝春秋):『おいしいごはんが食べられますように』を読んでいるあいだ、時折脳裏によぎった作品。2019年本屋大賞受賞作です。2021年10月に映画化もされました。一見不幸な生い立ちながら前向きさを感じさせる作品は、『おいしいごはんが食べられますように』と対局の位置に存在しているように感じます。
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪