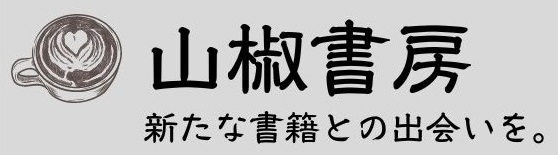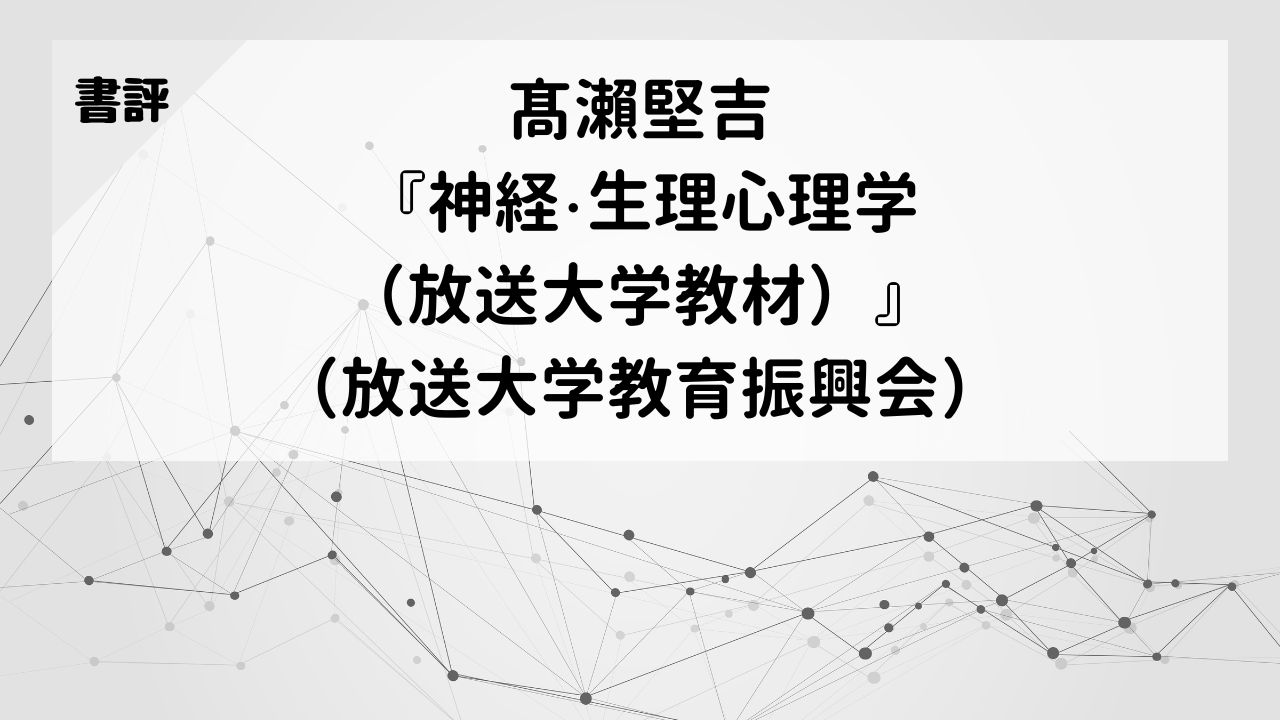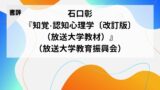先日公開した「知覚・認知心理学」の記事でも少し触れましたが、実は私は、かつて4年制大学で生理心理学の要素を含む卒業論文を提出したことがあります。その研究は、脳波(EEG:Electroencephalogram)やその他の測定値から、仮説を検証するというものでした。
しかし、当時通っていた大学では生理心理学の授業が開講されておらず。指導教員や先輩から論文や機材の使い方・データの取り扱い方を教えてもらったり、独学で勉強したりという日々。結果として、卒業論文を仕上げるに充分なスキルを身に付けることはできたものの、「脳のことを体系的にきちんと学びたいな…」という思いが心の片隅にずっとありました。
そして、あれから十何年…! 満を持して受講したのが「神経・生理心理学」です。図がたくさん掲載されているので、本書に何度も登場する脳の部位のざっくりとした配置状況は、読み進めるうちにわりとよく覚えることができたと思います。
本書ではノーベル生理学・医学賞を受賞した利根川進先生の、近年の研究も紹介されていました。利根川進先生のお名前は知っていたものの研究内容はまったく無知だったので、大変勉強になりました。そして、これは想定内ではありますが…やはり生物学的観点での記述が豊富であるがゆえ、印刷教材(テキスト)は他の科目と比べて若干ぶ厚めです。
今回は、生物学的知見を通して人の心と身体の関係を考えてゆく「神経・生理心理学」の印刷教材(テキスト)をご紹介します。
書籍は全国の書店などで購入できます。放送大学生でない方も、本科目の講義はBS放送などのテレビで視聴可能です。詳しい視聴方法は以下をご参照ください。
放送大学科目の書評記事のまとめはこちら
放送大学の科目についての書評記事は以下にまとめました! ご興味あればご参照ください♪
本講座の基本情報
本講座「神経・生理心理学」は、放送大学で開講されている科目です。
- 2022年度開設(2026年度に改訂予定)
- 放送授業(テレビ配信)
- 心理と教育コースの専門科目
具体的なシラバスはこちらからご参照ください。
放送授業はテレビで公開されており、書籍はAmazonほか各書店でお買い求めいただけます。各地域におけるテキスト取扱書店は下記をご参照ください。
こんな方にオススメ
- 生物学的な知見から人間に関する理解を深めたい
- 公認心理師を目指している
- 心の病への理解を深めたい支援職・教育関係者
目次
本書の目次は下記のとおりです。全15回の放送授業に沿った章立てとなっております。
1 神経・生理心理学への招待
2 心の生物学的基礎(神経系①)
3 心の生物学的基礎(神経系②・内分泌系)
4 外界を知覚する仕組み①
5 外界を知覚する仕組み②
6 記憶の生物学的基礎
7 学習・認知の生物学的基礎
8 情動の生物学的基礎
9 意識の生物学的基礎
10 コミュニケーションの生物学的基礎
11 睡眠・生体リズム
12 遺伝子と行動
13 心の発達の生物学的基礎
14 心の病気の生物学的基礎
15 まとめと展望
生物学の基礎知識を理解する
かつて通っていた4年制大学では生理心理学の科目が開講されていなかったと冒頭で述べました。これは、当時の心理系学部の学生は、高校で文系を選択した者が圧倒的に大多数を占めていたというのが一つの理由かと思います。おそらく心理学を学ぶ学生は、今でも文系出身者が多いのではと想像しています。
実際には心理系科目は文理融合的な内容が多く、統計解析に代表されるような理系要素を多分に含んでいます。しかし、学生の多くは臨床心理学のような対人カウンセリングに関心があり、文系的なイメージを持って入学することが多いようです。
私は生物学は関心があり好きな方なのですが…、それでも理解の定着に手こずりました(マジで)。完全な理解を目指すなら、必ず充分な勉強時間を確保できるよう、公私の予定を付けてから学習することをオススメします。
本科目を履修しているあいだ、以前履修した「人体の構造と機能ー人体の構造と機能及び疾病Aー」「疾病の成立と回復促進ー人体の構造と機能及び疾病Bー」の内容を振り返ったりしました。この2科目は公認心理師の受験資格取得にあたって履修必須の科目で、生理学的基礎を学ぶことができます。
そのほか、「知覚・認知心理学」の内容も一部重複しているので、同時並行で受講しながら理解していくようにしました。と、このように、本科目だけでなくほかの生物学系科目も履修することで理解がさらに深められるハズ!
ただ、どの科目を最初に学ぶかは学生が自由に決められる都合上、印刷教材(テキスト)はどの科目も丁寧に作られています。本書も同様です。
読者の皆様が、心理学の概論的知識を持ち、さらに数学、物理学、化学、生物学の知識が備わっていると、本書の理解はより容易になります。しかし、これらの予備知識がなくても理解しやすいように、本書では平易な説明を心掛けました。
引用元:髙瀨堅吉『神経・生理心理学(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
本書には図が多く掲載されていますので、何度も読むことで理解の定着をはかることは可能です。そして、章末の演習問題が大変役立つ。単語の穴埋め形式なので、しっかり真面目に取り組んでいけば「初めて聞いたぞ…」という新出単語をも着実にモノにしていくことができるでしょう。
脳の機能を心理学の各領域と関連づけて学ぶ
とにかく脳の各部位に関する用語がたくさん登場します。ここが難解に感じるところではありますが、これまで学んできた心理学の他の分野の各知見について、脳のどの部位が関係しているのかということが分かるのは、とっても面白いです。
たとえば、学習心理学の分野で必ず学ぶであろう「オペラント条件づけ」については以下のとおり。
オペラント条件づけの成立には強化と、その背景にある動機づけが重要な役割を果たす。この強化ならびに動機づけの神経機構は脳内自己刺激の研究から、腹側被蓋野から海馬、扁桃体、側坐核、前頭連合野などへ投射するドーパミン作動性神経の働きであることが報告されている(図7ー5)。
引用元:髙瀨堅吉『神経・生理心理学(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
心理学を学ぶ学生なら、「レスポンデント条件づけもオペラント条件づけも知ってるよ!」という人はきっとたくさんいるでしょう。でも、私は「ドーパミン作動性神経」といった観点から考えたことはこれまで一度もなく、本科目を学ぶことで新しい視点を得ることができました。
放送授業では、講師の髙瀨堅吉先生が頭の模型をパカッと開いて「ここですね」と指し示してくれます。印刷教材(テキスト)の図解と比較しながら、この模型で立体的に脳の部位を理解することができてとても良いです。模型の頭を開く「パカッ…」の瞬間には、謎の緊張感がありました(私だけ?)。
しろうと理論
神経・生理心理学の知識が無い状態でも、カウンセラーになることは可能です。しかし、本書では「しろうと理論」の観点から、神経・生理学的知見の理解を勧めています。
(中略)心理学ではよく言われることだが、人(素人)は他人の行動や自分の行動を説明する際に独自の理論や信念、すなわち「しろうと理論」を用いる。しろうと理論は自分や他人の行動に影響を及ぼすので、その理論が作られる過程や、その理論が行動に与える影響力は心理学の研究対象にもなっている。これは神経・生理心理学的知見についても同様である。例えば、神経・生理学的知見を含まない心理学の知識を備えていたとすると、心の病や神経発達症の病名や症状を知っているので、身近な人がそれに罹患した場合に、発症自体には気づくことができる。また、臨床心理学を詳しく学んだならば、その症状について理解し、介入することもできるであろう。ただ、先に述べたしろうと理論からもわかるように、人は「わからないこと」に、あれやこれやと想像をめぐらす生き物である。神経・生理学的知見を含まない心理学を学んだ場合、心理学に関するしろうと理論の生成は抑えられても、神経・生理学的知見に関するしろうと理論の生成は抑えられていないので、病状の適切な理解が阻まれるだろう。結果として、これは良い事態に至らない。
引用元:髙瀨堅吉『神経・生理心理学(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
ちょうど本書での学びを終えたあとに読んだ、ドナ・ウィリアムズ(Donna Williams)著『自閉症だったわたしへ(原題:NOBODY NOWHERE)』(新潮社)で、「あ! これが神経・生理心理学を学ぶ意義かも!」とハッとした部分がありました。
著者のドナ・ウィリアムズ氏は、本のタイトルのとおり後に自身が自閉症であることを知るのですが、その過程で何度も深刻な体調不良に陥ります。その原因を調べたところ、なんと彼女が食物アレルギーや化学物質アレルギーを複数持ち、深刻な低血糖症であることが判明するのです。
そして、食事療法によってコミュニケーションの問題が劇的に改善していく、という記述がありました。
食事療法を始めてから最初の数週間で、わたしが働いていた店の主人は、すっかり目を丸くした。わたしはお客たちに向かっておだやかに、辛抱強く話すようになっていた。たとえ、お客たちの方がいらいらしているような時でもだ。急激に気分が変わることもなくなり、それとともに、人とうまくやっていくことができるようになったのだ。時として浮かれて騒がしく、攻撃的にさえなっていたわたしが、はるかに物静かになり、温和ではにかみがちな人間になった。しかしそれでも、わたしの心の奥深くの情緒的な不安定とそこから起こる社会的なコミュニケーションの問題は、まだ、消えはしなかった。
引用元:ドナ・ウィリアムズ(著)、河野万里子(訳)『自閉症だったわたしへ』(新潮社)
本書では、この食事療法を開始してから、紆余曲折はあるもののドナ氏の混乱が徐々に落ち着いて行く様子が描かれています(しかし、引用部分の最後に書かれているように、コミュニケーションの問題が即時解消したわけではない)。
さらに、ドナ氏自身は、代謝やアレルギー(身体)の問題と、脳(心)の損傷とは関連があるのではないかと疑っています。
またわたしの場合、その悪循環は、複雑な食物アレルギーによっていっそう断ち切りにくいものになっていた。深刻な食物過敏症を治療せずにほうっておくと、栄養素の吸収がうまくいかないために栄養不良となり、体内には毒素がたまって、脳に損傷をきたす恐れがある。一方、代謝に何らかの問題があると、さまざまな食物を適切に摂取することができなくなり、それが食物過敏症につながることもある。つまり脳と食物過敏症は、相互に関連し合っているのだ。食物過敏症は脳の損傷を招く恐れがあるが、逆に、脳の損傷が食物過敏症を招く場合もあるわけである。
引用元:ドナ・ウィリアムズ(著)、河野万里子(訳)『自閉症だったわたしへ』(新潮社)
人の心と身体は繋がっている。だからこそ、支援職はカウンセリング理論だけに頼らず、幅広い視野を持って神経・生理学、その他さまざまな教養を深めていかなければならないのだろうなと思いました。
神経・生理心理学はアニマルウェルフェア(動物福祉)など倫理的な課題を内包していると思うのですが、そこから得られた知見は有意義です。少しずつ学んでいきたいです。
関連書籍
- 石口彰『知覚・認知心理学〔改訂版〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):公認心理師資格取得に必要な科目です。「考える」ことについての科学、という形で、知覚心理学と認知心理学の知見をまとめた一冊です。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 坂井建雄、岡田隆夫『人体の構造と機能〔改訂版〕: 人体の構造と機能及び疾病A(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):公認心理師資格取得に必要な科目です。公認心理師を目指さない場合でも、生物学的・解剖学的な観点での基礎知識を得たい方はこちらの一冊が有用です。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 岡田忍、佐伯由香『疾病の成立と回復促進〔改訂版〕: 人体の構造と機能及び疾病B(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):こちらも公認心理師資格取得に必要な科目です。疾病に関する基礎や代表的な疾病の特徴およびその経過について学ぶ一冊です。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- ドナ・ウィリアムズ(著)、河野万里子(翻訳)『自閉症だったわたしへ』(新潮社):自閉症の当事者が出版した本として大変有名です。訳者の河野万里子さんは、2006年に『星の王子さま』(新潮社)の新訳も担当なさっていました。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪