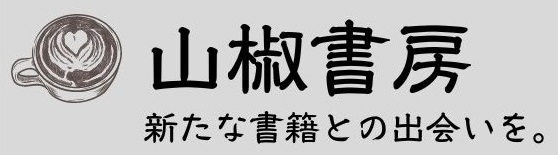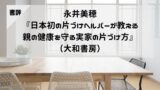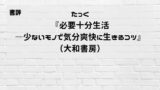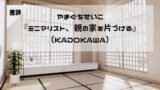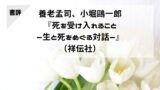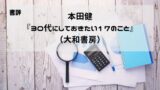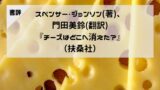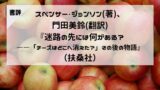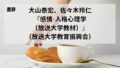2023年1月にX(旧Twitter)で記録しはじめた捨て活記録が、2025年10月で1000日に達成しました! せっかくなので、この1000日のあいだに捨ててきたモノや、自分の人生の変化について振り返ってみます。
かなり長文になりました。主に自分としての「区切り」という位置づけで作った記事ですので、目次を見て気になる点があればその部分だけお読みいただく形でも良いと思います。それでは、しばしお付き合いくださいませ!
捨てたもの・手放したモノを記録していく
捨て活をはじめたきっかけ
捨て活の記録をはじめる前
記録開始は2023年1月ですが、実は、2020年頃からゆるゆると捨て活をはじめていました。捨て活を始めたきっかけは、2021年の引っ越し準備です。祖父と父の体調悪化に伴い、それまで東京都内で一人暮らししていたところを実家に戻る決意をしたのでした。要するに、捨て活のきっかけは家族の介護問題です。
この賃貸マンションには、計8年間暮らしました。周辺地域の相場と比較すると若干家賃が高かったのですが、大家さんが最上階に住んでいて、駅近でとても良い物件でした。職場や都内各所へのアクセスも良好、今でもとても良い思い出でいっぱいです。
終電で帰宅したりという日もあってなかなか残業の多い仕事だったので、モノはそこまで多くないものの部屋のなかが散らかっていました。私は物欲があまりない方なのですが、日常的に図書館に通う活字好き。セミナー資料やおしゃれな空き箱、参考書、気になる書籍の積読などが床の上に放置されていました。
そこで、まずは不用品を処分せねばと古い衣類を捨てたり、書籍などをフリマサイトで売却しはじめたのでした。
捨て活の記録開始!
そうして、2021年秋に実家に引っ越します。この頃はコロナ禍まっただ中で、すでに在宅勤務が広がっていました。私の会社も同様で、始業前やお昼休みの時間を使ってせっせと祖父の不用品を処分していていきました。
そんななか、約半年後の2022年春にやましたひでこさんの『1日5分からの断捨離―モノが減ると、時間が増える』(大和書房)という本に出会います。この本を読んで、「1日5分でもいいから進めていこう!」と決意。実際には毎日はできなかったのですが、それでも少しずつ進めていきました。
年が変わって2023年。お正月を過ごしながら、「年の初めだし、新しいことをやろう…」と考え、手放したモノを記録することに決めます。毎日5分でも進めて、記録することで成果を確認していこうと閃いたのでした。
頭の中に浮かんだのは「レコーディングダイエット」です。私は中学・高校時代に自分の体重と体脂肪率を毎日記録しており、その時の経験から「記録し続ければ、現状確認と目標への軌道修正につながる」という確信がありました。
幸か不幸か「何かをやり続ける」ということに適性があるタイプなのだと思います。そこで、それまでは読書記録専用として活用していたX(旧Twitter)にポスト(ツイート)してゆくことにしました。
記念すべき最初のポスト(ツイート)はこちらです。さて…「レゴブロックの置物」というのがなんなのか、今ではすっかり思い出せません(笑)まぁ、後になって思い出せない程度のモノだったということで、手放してよかったと考えています。
家族を巻き込み、捨て活を加速
X(旧Twitter)での記録を開始してから、祖父母のモノや、自分が実家に残して放置していたものの整理に特に注力しました。実家は二世帯住宅で、1階が祖父母の居住空間、2階が両親の居住空間になっていました。
祖父の介護に主に時間を割いていたのは母で、父自身は体調を崩していました。そんなことから、私が主体となって祖父母のモノの整理をしていたのですが、仕事の変化や私自身の体調不良もあって限界を感じていました。
家族内で何度も衝突を繰り返しました。とにかく「現状のままではいけない」ということを話し、週末に母の力も得て生前整理・遺品整理を進めていきました。実は、きょうだいが将来的に両親と同居するという話も上がっていました。
ここで、家族の力を得るうえで、引っ越し前に経験していたフリマサイトでの売却が役立ちました。モノが売れてお金に変わると、みんな喜ぶのです!!
「老後はどうなるかわからないし、いらないモノは売ってお金にしていこうよ」と、実利的な面でのメリットがある点をみんなで共有しました。こうした経緯もあって、X(旧Twitter)での捨て活記録には家族が手放したものも含まれています。
継続の秘訣
ハードルを下げる
「継続する」ということが第一の目標なので、とにかくハードルを下げることにこだわりました。そのために、5つのルールを設けていました。
- 1日1個だけ捨てる
- 日用品の使い切りもカウントする
- 投稿ネタをストックしておく
- 雑紙、DM、レシートもカウントする
- 写真は撮らない
その一つが、「1日1個だけ捨てる」というルールです。実際には、1000日間をとおしてほぼすべてのポスト(ツイート)で1日1個以上を処分しているのですが、それはそれ。「1日1個だけ捨てる」というルールなら、継続できました。どんなに忙しくても、1日1個だけなら達成できそうな気がしませんか?
2つ目は、「日用品の使い切りもカウントする」というルールです。祖父がシャンプーのストックを大量に遺していたこともあって、これらの処分も兼ねて使い切り品もカウントすることにしました。食料品は、日常的に処分される流れにあるか否かでカウントを分けました。牛乳パックやペットボトルはもともとすぐに処分するタイプなのでカウントしない、期限切れ食品は自分で主体的に手放さなければ処分されないのでカウントする、といった具合です。
3つ目は、「投稿ネタをストックしておく」というルールです。どんなに疲れていても、毎日継続する仕組みは作っておきたいものです。私の場合は、ポスト(ツイート)に記載したモノ=その日手放したモノではありません。これには、粗大ごみ処分やフリマでの売却にあたって身バレ防止の意味も込めています。
4つ目は、無意識に捨てがちな「雑紙、DM、レシートもカウントする」というルールです。本当に忙しい時には、次のような形で継続することができました。まず重視すべきなのは「継続すること」であって、「たくさんモノを捨てること」ではありませんでした。あと、単純にどのくらいの紙類が家のなかに存在しているのかということにも興味があったので、原則枚数はカウントすることにしました。
最後に、「写真は撮らない」というルールです。光加減など配慮して写真を撮ることを考えると、手間がかかります。あと、単純に写真を撮るのが下手というのもあります。写真を載せればインプレ数を稼げそうですが、特に注目してもらいたいという思いはありませんでした。身バレのリスクもあるし、自分にとって本当に思い入れのあるものなら公開する必要はないかなと考えました。
投稿フォーマットをつくる
疲れているときでも、あまり悩むことなく継続できるように投稿フォーマットを定型文としてあらかじめ作っておきました。私の場合は、こんな感じです。
🗑️=ゴミ
♻️=資源ゴミ
💰=フリマ
✨=その他
捨てるという行為は、罪悪感を伴う行為です。「うまく活用できなかった」「大量生産・大量消費によって地球を壊している」「お金が無駄になった」。しかし、罪悪感で行動せずにいると自宅が崩壊していきます。
よって、この罪悪感を少しでも減らすために、できるだけ「資源回収に回す」「売却して他の方に譲る」「寄付する」というやり方を常に意識したいと考え、このフォーマットにしました。
X(旧Twitter)上でも、ときどき記載ルールを公開しています。
捨て活仲間から刺激をもらう
投稿の際は必ず「#1日1捨」「#捨て活」「#遺品整理」などのハッシュタグを付けました。そうしているうちに、一緒に捨て活をしている方がオススメに表示されるようになりました。
他の方のポスト(ツイート)を眺めていると、共感や発見の嵐です。ただ、最初の頃は「これ、まだ使えるのに捨ててしまうの…? 勿体ないなぁ」という感想が浮かぶこともしばしば。世の中にはいろいろな価値観があることを学びました。他の方が捨てたモノを見て自分も同じモノを捨てようと決心したこともありましたし、逆に自分が手放したモノに共感していただくこともありました。
手放されたモノからは、その人の人生が垣間見えるものです。「みんないろいろなものを抱えながら生きているし、悩みながらも片づけをとおして人生を前に進めているのかもしれない…」と考えるようになりました。
片づけというのは自分の居場所を整える行為であり、人生を主体的に生きていくことにつながる。「自分自身の人生を生き抜くためにも、捨て活で不要なモノを手放し、これからに必要なものだけ手元に置いていこう」という思いが強くなっていきました。こうして、必然的にモチベーションはあがっていきました。
捨てたモノ
無料で貰ったモノ
うちわ
プラ製うちわに竹製うちわ、紙製うちわ。90年代~00年代は家電量販店前や駅前などでよくうちわが配られていました。それらをあちこちに点在させながら律儀に保管していたのでした。なんと、捨て活1000日目までに捨てたうちわの数を確認したところ、全部で207点ありました。
沸騰時代といわれる令和においては、残念ながら自宅でも外出でもうちわだけで涼をとることができません…。まさに命にかかわる猛暑が続いているわけです。うちわを200点以上持っていても今後活用の機会はないので、処分しました。
私の自治体では、紙製うちわは資源ゴミ、竹製うちわ・プラ製うちわは不燃ゴミでした。処分の際は、自治体のルールに従って分類して捨てましょう。
紙類(リーフレット・パンフレット、雑誌・新聞記事の切り抜き、封筒、名簿)
「必要だから取っておこう」の代表格が紙類だと思います。雑誌・新聞の切り抜き、レシート、旅先でもらったリーフレットにパンフレット…。祖父は活字好きなこともあって、新聞記事のシリーズ連載や雑誌の連載小説をすべて切り抜いて保管していたのでした。
さらに、こうした紙類の分類に祖父は大きめの封筒を活用していたようです。封筒というのは、郵送物として使われて自宅に届いたA4封筒などです。シリーズ連載ごとに保管用の封筒を用意して管理するという使い方です。予備の封筒だけでも200枚くらい保管されていました。
そこで、個人情報はすべて油性のボールペンで一つ一つ塗りつぶし、封筒を資源ゴミとして捨てました。ちなみにこのボールペンは銀行さんや店頭配布で無料でもらったものなので、不用品(ボールペン)を使って不用品(封筒)を手放していったということになります。
紙類は雑紙という形でまとめてカウントしている場合もあるので、正確には何枚捨てたか今では不明ですが、雑誌・新聞の切り抜きだけでも約10,000万枚は捨てているようでした。ですので、雑紙という大枠で見れば10万枚くらいは捨てていそうです。
1日で9cmの厚みが出るほどの量を捨てたことも。
まだデジタル化が進んでいない昭和世代の退職後は、所属団体・組織や大学のOB名簿が定期的に自宅に届けられていました。祖父の関係者ならすでに他界している可能性も高かったのですが、個人情報をそのままゴミに出すわけにもいかないので、名簿は1枚1枚ページをちぎってシュレッダーにかけて処分していきました。
ライター
父はかつて喫煙者でした。以前はコンビニでタバコをカートン買いすると毎回無料でライターがもらえたようで、使い切りもしないのに大量に保管されていました。自宅にライターが大量に保管されているのはとても怖いものです(マジで危ない)。
中身が入っているライターはそのままゴミに出すことができません。知人にあげたり自分でガス抜きしたりして200本以上を捨てました。
ガス抜きは面倒ですが、思ったよりも簡単にできます。以下のようなサイトで確認してみてください。「面倒くさい」「捨て方が分からないから捨てない」という考えは、かなり危険です。
ペットボトルのおまけ
平成中期によく見られた光景ですが、ペットボトルにはよくおまけがついていました。キーホルダーだたり、フィギュアだったりです。父が日常的に購入していた飲み物にもおまけがついていまして、そのため自宅に大量のおまけが保管されています。こちらは残念ながらまだうまく捨てきれていません。一部はフリマで販売したところ、売れました。
大切なモノと思い込んでいたモノ
カセットテープ、ビデオテープ
昭和~平成時代を生きてきた人びとにとって親しみがあるカセットテープやビデオテープ。思い出のラジオやテレビ番組、ホームビデオが保管されていたのです。しかし、大切なモノではありながらも残念ながら再生機器がありません。そう、中身が確認できません。
使用済みのカセットテープはすべて可燃ゴミで処分、思い入れがあるホームビデオはカメラのキタムラさんのダビングサービスでDVDにダビングしました。ビデオダビングの「2025問題」があると言われているので、ダビングにはちょうどよいタイミングだったなと思います。あと数年遅かったら、大切な記録がすべて消え失せるしかなかったのかもしれません。
写真
祖父は退職後に写真サークルに入っていたので、たくさん写真が保管されていました。仕分けしてみると自分や他の家族が幼かったころの姿なども発掘されましたが、思ったよりも旅行での観光写真が多いことに気が付きました。
しかも、旅先で出会った人に声をかけて写真をとっていたりと、残された家族にとってはもはや何の意味もない写真…。
風景だけの写真は可燃ゴミ、人が写っている写真は祖父を弔った葬儀社が主催している供養祭で処分していくことにしました。写真のネガやスライドは可燃ゴミです。こちらは現在進行形で整理を進めています。
イベントグッズ、旅行用アイテム
クリスマスツリーや雛人形、五月人形など特定の季節にだけ取り出されるグッズは処分していきました。考えてみれば、どれも20年以上は確実に使用していません。雛人形は祖父を弔った葬儀社が主催している供養祭へ。雛人形を買ってもらった娘自身が処分するのが良いと聞いたので、母(祖父母が母に購入したものでした)が処分しました。雛段は金属なので資源ゴミです。
五月人形も同様に、買ってもらった息子(私のきょうだい)が処分するのが良いと聞いたので、きょうだいに渡して処分してもらいました。
七五三の着物や草履、子ども用の浴衣はすべて処分しました。お食い初めセット(机など)も見つかり、処分しました。
旅行の際に使用するスーツケースやキャリーケースも在庫が過剰だったので処分しました。古くて汚れていたり、キャスター部分がガタついていたりと使用に耐えない状況でもあったので、より小さなサイズの新しいものを購入し直しました。
せっかく購入したので、旅行の際のみ使うのではなく、少し遠出したり荷物が多い移動の際に活用するようになりました。こうすることで、経年劣化する前にモノに対して十分な活用機会を与えることができるようになりました。
人から貰ったモノ
母の伯父(祖母の兄)からもらったという日本人形がありました。そこそこ大きく、またとてもキレイな状態でしたが、なぜいただいたのかも現在では分からず。伯父はすでに他界していることもあり申し訳なさはありましたが、祖父を弔った葬儀社が主催している供養祭で処分してもらいました。
亡くなった祖母からもらった旅行土産も、なかなか捨てるという判断に踏み切れませんでした。なんてことはない2001年のカレンダーなのですが、翌年2002年に祖母の病気が発覚したということもあって、そのままにしていました。捨てずに取っておいてあるからといって大切にしているわけでもなく、ふだん意識に上ることもない。そこで、「このまま持ち続けていても意味はない」と過去に区切りをつけて手放しました。
子どもの頃の思い出の品
私は立派な平成女児だったので、おもちゃに恵まれた時代を生きてきました。大量のおままごとグッズにぬいぐるみたち。おままごとグッズは思い出はありつつも、自分が今後使うことはありませんし、親族の子どもたちには新しいおままごとグッズを買い与えるのが良いだろうと考えました。このため、ほとんど処分しました。
ぬいぐるみたちは、お土産などで両親の知人や祖父母から買ってもらったものがたいへん多かったです。ぬいぐるみを手放すのはとても心苦しいものです。以前、マンションのゴミ捨て場で清掃員の方が、ゴールデン・レトリバーの大きなぬいぐるみをガシッと掴んで仕事をしていたのを、車で移動中に見たことがあります。
「あぁ…あの可愛い犬のぬいぐるみ、持ち主はどんな気持ちで一緒に過ごして、手放したんだろう」と切なくなり、自分の捨て活と紐づけて考えてしまいました。「自分はぬいぐるみをゴミとして捨てることができるのだろうか」と。
私のぬいぐるみはまだあまり手放せていませんが、きょうだいの分と合わせて30点ほどを、祖父を弔った葬儀社が主催している供養祭で処分してもらいました。残りのぬいぐるみたちは、同じく供養か寄付という形で手放していこうと考えています。
大量の本
本というのは人生を豊かにしてくれるもので、大人になってから読書好きになった私にとって手放すのがとても辛いモノでした。このため、フリマサイトでの売却や図書館のリサイクル本コーナー(利用者が自由に置いたり持ち去ったりできる棚)への配置を基本に手放していきました。
地域の古本屋にも声をかけました。これまでの実績をカウントしたところ、祖父・父・兄の本だけで約500冊ほどは手放したようです。
捨て活を始めた当初は、祖父の書斎やクローゼットのなかから発見された本をざっと眺めてみただけでも、4桁の本はありました。ということで、この500冊を手放してもまだまだ本に溢れているというのが実態です。
本は自分の人生を変える知識や癒し、喜び、発見を与えてくれます。最近は読書離れが進んでいると言われますが、こうした魅力から読書を愛し続ける人というのは今後も必ずいるでしょう。祖父がまさしくそうでした。
その後、自分も読書好きになり、遺品整理に多くの時間を取られた経験があるからこそ思うのですが、どんなに大切な本であっても残された家族にとってはそこまで重要なものではありません。だから、自分が存命のうちに大切な本の処分は自分である程度考えておくことをオススメします。
ちなみに祖父の場合は、書斎から発見された1枚の紙に「○○の本と△△の本は保管し続けること。その他の本は処分して構わない」といった意味のことばが遺されていました。それを見た家族の感想としては、「それは分かったけど、元気なときに本は自分で処分しておいてくれれば良かったのに…」でした。
衣類
遺品整理のほとんどは多趣味な祖父の私物でしたが、オシャレ好きな祖母がたくさん洋服を持っていました。実は、祖母、母、私は体形がかなり似通っていたのでした。そこで、祖母の遺した衣類はおさがりとして母と私が着用したりしましたが、あまりに数が多く限界がありました。自分の趣味や時代に合わない衣服を着続けるというのも辛いものです。
ただ、よくよく見てみると衣類もだいぶ傷んでいることが分かります。一般的には女性の方が長寿といわれています。しかし、我が家の場合は祖母が他界して17年後に祖父が他界しました。生前の祖父に遠慮して祖母の遺したモノを処分しないでいるうちに、オシャレな衣類も劣化していたのです。祖母の分だけで、資源ゴミとしてトラック1~2台分くらいは手放したかと思います。
父も在職時にスーツやネクタイ、Yシャツをたくさん抱えていました。体形がすぐに変わる(太りやすい)ので、さまざまなサイズの衣類が大量にありました。なんにせよ、退職したいまはどれも着用しないので原則すべて資源ゴミとして処分しました。
衣類の処分に伴い、ハンガーラック4点とハンガー500点を手放しました。
こうした明らかな不用品を手放しているうち、いつか雑巾にリメイクして活用しようと保管していた古いタオルも不要なことに気づき、処分しました。
コレクション
大切だからと未使用のまま保管していたコレクション。そこそこ高額でレアなものもあることでしょう。父は長年あるスポーツチームの大ファンで、年会費はもちろんのこと特集番組は必ず録画して、視聴者プレゼントにもコツコツ応募するという生活をしていました。
家族はあまり知りませんでしたが、スタジアムでもグッズをコツコツ購入していたようです。それが、体調を崩して気軽に外出できない状況になったことから、少しずつ過去に集めたグッズを手放していくことになりました。
見ていて思うのは、未使用のモノがほとんどだったということです。本来モノは使われてナンボですが、コレクションというものはキレイな状態を維持するために未使用のまま保管されているのです。未使用でも汚れがあるものは処分しましたが、キレイなものはフリマサイトで売却していきました。
処分の際に活用したモノ
ボールペン
紙類の処分のところで触れたとおり、無料でもらったボールペンは個人情報消去の際に活用しました。
書き損じはがき・切手
祖父と父がコレクションしていた切手はこれまで何度も売却してきたのですが、一部はそのまま保管していました。整理の都度発見される書き損じはがきと未使用切手は、少しずつ郵便局へ持ち込みスマートレター(2024年9月までは180円、2024年10月以降は210円)へ交換していきました。交換の際は手数料が発生しますが、そこはガマンです。
交換したスマートレターは、フリマサイトで売れた品の発送に活用しました。新書や文庫本の発送にとても役立ちます。これにより、送料に不要切手を活用することができました。スマートレター以外の普通郵便で、切手を貼って郵送することもありました。
シュレッダーごみ、ペット用おむつ・シーツ
シュレッダーで裁断された紙類は、資源回収に回せません。そのまま可燃ゴミとして出すのもアリなのですが、せっかくなので何かに活用したいと考えました。そこで、液体モノ(古いお掃除グッズや食品)のゴミを処分する際に、液を吸い込ませる用途に活用しました。
また、我が家では過去に犬を3匹飼っていました(1匹は捨て活中に他界)。シニア犬とともに暮らした経験がある方はよくわかると思いますが、排尿が困難になるため犬もおむつを着用するようになります。これらのゴミも可燃ゴミにそのまま出すのではなく、液体モノを吸収させる用途で活用しました。
紙袋、ビニール袋
お店からもらった紙袋は、状態が良いモノであればフリマサイトでの梱包物に活用、状態が悪ければ資源ゴミを出す際の袋として活用しました。
かつてはレジ袋を無料で配っていたこともあり、祖父母は数百枚のビニール袋を保管していました。あまりに多すぎるので、劣化したものほとんどのビニール袋はゴミとして処分しましたが、一部は不燃ゴミを処分する際の袋として活用しました。
寄付したモノ
ペットグッズ(フード、薬、おむつ、シート)
捨て活中に旅立った愛犬のために保管していたフードは、知人と動物病院へお譲りしました。病院から処方された薬や犬用おむつ、シートも何かの役に立つかと思い、動物病院へ寄付しました。特に犬用おむつは、急激に体調が悪化した愛犬のために旅立つ1週間前に購入したばかりで、ほとんど新品の状態でした。
お世話になった動物病院は保護犬や保護猫の支援に積極的な病院なので「どれも保護の仔に活用させていただきます。助かります」ということでした。
使用済みカイロ
一般社団法人Go Green Japanさんという団体が、使用済みカイロを集めています。父がよくカイロを使用するので、使用済みのモノはこちらに寄付しました。郵送時には、祖父が保管していた未使用切手を活用しました。
使用済み切手
祖父の書斎を整理していたところ、使用済み切手を保管していたことが分かります。父も同様で、使用済み切手を缶に保管していました。これらは慈善団体に寄付しました。
経済的な観点での変化
不用品を売却
すでに言及しているとおり、フリマサイトや古本屋、ほかにも地域の不用品買取店に売却していきました。本の売却はあまり高額ではありませんが、チリツモでお金が溜まっていきました。
意外にも売れたモノは、未使用のカセットテープでした。すでに生産終了しているメーカが多いようで、海外からご購入いただくことが多かったです。
金価格が高騰していたこともあり、両親が結婚式の引き出物でもらった当時10,000円相当の金貨が、43,000円くらいで売れました。ほかにも不要な貴金属はこの機会に整理してもらいました。祖父と父がコレクションしていたコインセットが合計144,000円くらいになりました。
2022年の夏頃から不用品の売却額をきちんと管理するようになり、それを集計したものが以下の表です。なんと総額で70万円の利益になりました。なお、ここでは自分自身の不用品売却額は含んでいません。
| 年 | 売上個数 | 利益(総額) | 利益(平均) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33 | \25,374 | ¥769 |
| 2023 | 56 | ¥91,641 | ¥1,636 |
| 2024 | 59 | ¥274,428 | ¥4,651 |
| 2025 | 70 | ¥312,351 | ¥4,462 |
| 合計 | 218 | ¥703,794 |
利益(総額)の欄を見れば分かりますが、捨て活を続ければ続けるほど年単位での売却益の増加が加速していることが分かります。これは、家族みんなが自分の人生にとって役目を終えたモノを手放せば、どんどんお金に変わっていくということの証左であると考えます。
廃棄・処分費用に活用
ノートパソコンや金庫など処分費用がかかるモノ、供養に関する費用は売却益から捻出しました。フリマサイトでの梱包資材の購入にも活用しました。不用品を売却して得たお金で不用品を手放していくことで、経済的になんら私生活への悪影響を及ぼすことなく捨て活を続けることができました。
収益は投信積立で殖やす
売却益の記録開始時から、売却益は証券口座に移してバランス型投信を月3回積立購入していきました。そして、売却益が増えてきたら相場を見つつ増額していくという方式にしました。金利上昇に伴い預金金利が付くようになってからは、積立用資金を預金口座に移して利息を確実にゲットしていく方針に変更しました。
その後、相場を見ながら、追加で別の株式投信を月3回積立購入することにしました。これらの投信の運用益は、両親の介護や大物処分の費用、家族内で資金が必要になった際に活用するつもりでいます。そのため、利殖第一ではなくある程度低リスクの商品を選んで投資し続けています。
2025年秋時点で、積み立てた投信の総利回りは約15%となりました!
モノを購入するときにしっかり考えるようになった
商品を購入する際に、「これは不要になった時に売ることができるのか?」「処分の際にゴミの分別が面倒ではないか?」「割安で売られているが、すでに自宅にストックがあるのではないか?」などを考えるようになりました。
私はもともと財布のヒモが固い方であまりモノを購入しないのですが、家族は捨て活をとおして、これまでよりモノを購入するか否かにちょっと考えるようになったようです。これには、年金世代となったこともおそらく影響しています。
人生における変化
捨て活の記録開始前:天王星牡牛座時代がはじまった
天王星牡牛座時代って…?
私はときどき星占いの記事を読むのですが、そんななか見つけたのが「天王星牡牛座時代」ということば。星占いによると、2018年から2025年までの約7年間、変革の星である天王星が牡牛座に滞在するというのです。ざっくり言うと「牡牛座の人にとって大きな変革が訪れる」ということのようでした。
どの星占いを見ても、「牡牛座の人は2025年まで結構ハードな日々を過ごすよ」「でも、ちゃんと乗り越えられるよ」みたいなことが書いてあります。私はザワザワしました。そう、私は牡牛座なのです。そして、ちょうど2018年には祖母の体調が悪化し、2019年に他界したところだったのでした。
実際のところ、この天王星牡牛座時代が私にとってハードだったかというと、超超ハードでした。でも、乗り越えられました。そんな辛い日々を支えてくれていたのが、捨て活であったような気もします。
というのも、牡牛座というのは「モノに対する執着が人一倍強い」とされる星座です。私もモノを大切にするという気持ちが強い方で、モノ持ちがよくため込みがちなタイプです。そんな私が捨て活を1000日間、記録し続けたのでした。
相次ぐ家族の死と体調悪化
2020年に祖父が要介護3と認定されて介護施設へ入居し、2021年に私は引っ越します。2022年にはきょうだいが結婚、その1ヶ月後に祖父が他界しました。その4ヶ月後に、もう一人の祖父も他界。この間に父が要介護1の認定を受け、1ヶ月ほどショートステイ。
この時点で父は60代でしたが、二人の死の葬儀に出ることができませんでした。「このまま父が介護施設で暮らすとなると、お金はどのくらい持つだろうか」と母とそろばんをはじいたりしました(その後、要介護度は要支援2の認定へ変更されました)。
新型コロナウィルスの感染状況や変異株の登場など、社会的にも日々情報が更新される時代でした。日本という国で元首相が狙撃されたりと時代が大きく変わっていく時期でもありました。
実家で飼っていた愛犬は14歳になっていて、夜間の介助がはじまっていました。何度か体調を崩しており、犬の病気は悪化が速いことから特に神経を使ってお世話をしていました。
仕事ではわりと大きな案件の最終段階に入っており、キャリアの都合上、かつてより責任を担う場が増えていました。そんなこんなで自分は体調を崩してしまい、食欲低下や頭痛の症状が頻発していました。
日常の楽しみを作り出す
「辛いな」と感じて日々を過ごすなか、2022年に書評ブログを立ち上げました。それがこのブログです。引っ越し前から、実家での暮らしはハードになることが容易に想像できたので、これまでやってみたかったことをやろうと考えたのでした。
そこで、無料ブログサイトで以前掲載していた記事をこのブログサイトに移して始動。書評サイトは稼げないジャンルということでよく知られていますが(実際、収益は限りなく少ないです)、せっかくなのでアフィリエイトも付けました。
X(旧Twitter)での記録開始
新しい仕事
と、こんな具合で、捨て活の記録を開始する前からハードな時期ははじまっており、自分の人生においてこれだけ大きな変化が立て続けに発生したのは本当に初めてでした。おそらく、今後もここまでの変化は襲ってこないのではと思っています。天王星牡牛座時代も終わった訳ですし。
捨て活をしていた1000日間(2023年1月~2025年10月)は、こうした変化に耐性がついてきた頃に始まりました。
仕事が一段落したので、別の仕事に関わることになりました。この仕事では、しばしば夜間に急遽対応する必要がありました。すでに愛犬の夜間の世話が始まっていたため「寝ている愛犬を起こさないように…」といつも綱渡りの状態で日々を過ごしていました。
放送大学へ入学
家族の変化が落ち着き始めたので、2023年には放送大学に入学して心理学を学び直すことにしました。放送大学で学び続ければ、公認心理師という資格にチャレンジすることができます。「可能性は低いかもしれないけれども、スキマ時間で勉強できるからチャレンジしてみよう!」と考えたのでした。
愛犬の旅立ち
頑張ってくれていた愛犬が2023年冬に旅立ちます。副腎に腫瘍ができたことで、腹大動脈に血栓が詰まる血栓塞栓症でした。救急病院にタクシーで連れて行ったり夜通し看病しましたが、助かりませんでした。最期は徹夜で看病したため、2日間ポスト(ツイート)の更新が停止します。
自宅購入を決意
祖父が同時期に2人他界し、愛犬も虹の橋を渡ってしまった。父は少し回復傾向にあるし、今後きょうだいがこの実家に暮らすという予定がある。こんな事情から、悲しみに暮れるなか、私もそろそろ次の住処を考えねばと日々思いを巡らす時間が増えました。実は、愛犬の世話をしている時点から、今後の住まいのことについてはいろいろシミュレートしていました。
愛犬の旅立ちから3ヶ月後、よく知っていて馴染みのある地域に建設中のマンションが買い手を募集開始したことがわかります。このマンションは実家からも近く、家族に何かあった場合にもすぐに駆け付けられそうです。「とりあえず話を聞きに行ってみよう」と現地を訪ね、1ヶ月後には購入のサインをしました。
人間ドックで要再検査の診断
愛犬が腫瘍により旅立ったこと、また、がんに罹患経験がある親族がたくさんいたことから、人間ドックでがん検査を受けました。結果は、要再検査。「あぁ、やっぱりか。次にケアを受ける家族は自分なのかな…」とショックを受けて再検査を受けに行きます。とりあえず再検査したところでは腫瘤の増大は見られないので経過観察ということになりました。
要再検査の診断が下ったことで、残念ながらがん保険付きの住宅ローンに落ちてしまいます。ここでも「病気になるといろんなところで制約を受けてしまうんだ…」と大きなショックを受けます。世間的には、これまで低金利で借りられた住宅ローンに変化があり、金利上昇の波が寄せ始めていました。
ただ、その後この銀行では、がん保険が付かない一般団信の場合は金利が少し低くなるという商品設計になり、不幸中の幸いで住宅ローンの見通しが少し明るくなりました。愛犬が腫瘍により亡くなっていなければ人間ドックも受けなかったので、このときは愛犬に助けられたような気持ちでした。
自分の親族の病歴を考えるに「そう遠くない未来に闘病のステージに入るかもしれないから、できることはできるうちに何でも早めにやっていこう…後悔しないように」と決意します。そして放送大学の勉強も読書も捨て活も、続けていったのでした。
姪が誕生
周囲の同級生や同僚は、着実に人生を前に進めています。子育てに忙しかったり、順調にステップアップしていたり。自分だけが取り残されているような感じもあり「自分は何をやっているんだろう…」と気分が落ち込むときもありました。
「せめて老後資金はしっかり蓄えよう」「身の回りをきちんと整理しよう」と、その時々でできることを着実にこなしていくようにしました。
そんななか、姪が爆誕します。家族・親族というのは常に変動するもので、これまで他界ばかりだった身内に明るいニュースが広がりました。
再び引っ越し
前述したとおり、購入したマンションへ引越しします。再び一人暮らしをはじめたら、自分の時間がたくさん作れることに感動しました。このため、勉強時間の捻出がかなりしやすくなりました。
実家へは継続的に訪れ、生前整理・遺品整理の手伝いと私物の整理を進めています。
捨て活記録がついに1000日達成!
以上が、捨て活の記録1000日目までの出来事です。天王星牡牛座時代をなんとか無事に乗り切ることができました。
今後の予定ですが、放送大学でコツコツ取得してきた単位が溜まってきて、来年の上半期には公認心理師の学部カリキュラムのうち受講必須の「心理演習」「心理実習」の選考基準を満たす目途が立ってきました。
この選考は倍率20倍ほどと狭き門なので先に進めるかはいまだ不透明ですが、もう少し頑張ってみようかなと思っています。公認心理師取得には大学院への進学も必要になります。将来的に進みたい大学院について調べ続けていますが、論文ももう少し収集していかねばというところです。
捨て活は、可能な限り継続していきます!
書籍紹介
捨て活中に自分の肥やしとなった書籍を紹介していきます。
捨て活の継続へのヒント
- やましたひでこ『1日5分からの断捨離―モノが減ると、時間が増える』(大和書房):お祭り気分で一気にお片付けするのが性に合わない方は、こちらの本が大変参考になると思います。千里の道も一歩から。断捨離は毎日5分から進めていきましょう。記事にしましたので宜しければご覧ください。
生前整理や空き家相続のこと
- 永井美穂『日本初の片づけヘルパーが教える親の健康を守る実家の片づけ方』(大和書房):親が健康なうちから環境を整えるならこちらの本がオススメです。別記事でも紹介していますので、宜しければお読みください。
- たっく『必要十分生活―少ないモノで気分爽快に生きるコツ』(大和書房):男性目線で語るロジカルな片づけの本です。これまで何気なく続けていた習慣は、本当に必要だったのか? など発想の転換を促してくれます。記事にしましたので宜しければご覧ください。
- やまぐちせいこ『ミニマリスト、親の家を片づける』(KADOKAWA):ミニマリストが親の家を片づけた実体験を追体験できる一冊です。認知能力の低下した両親が快適に生活できる仕組みに言及していて、学びが多いです。別記事でも紹介していますので、宜しければお読みください。
- 如月サラ『父がひとりで死んでいた 離れて暮らす親のために今できること』(日経BP):父親が孤独死をして空き家問題に直面した著者のエッセイです。両親の介護が気になり始めた方にはかなり響く内容です。記事にしましたので宜しければご覧ください。
喪失体験
- 小川糸『ライオンのおやつ』(ポプラ社):瀬戸内の島にあるホスピスが小説の舞台です。おいしい食べ物がたくさん登場する号泣作品。読むだけでおいしい作品なのだけれど、とにかく涙が止まりません。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 養老孟司、小堀鷗一郎『死を受け入れること ー生と死をめぐる対話ー』(祥伝社):生きている限り、身近な人の死は避けられません。解剖学者と訪問診療医の対談集です。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
世代特有の悩み
- 壇蜜『三十路女は分が悪い』(中央公論新社):みんなご存じ壇蜜さん。女性に好かれるグラビアアイドルってわりと稀有な存在ですよね。壇蜜さんに寄せられた相談への回答に勇気づけられます。記事にしましたので宜しければご覧ください。
- 本田健『30代にしておきたい17のこと』(大和書房):仕事も私生活も変化が多いのは、自分だけに限ったことではないのだなと感じさせられた一冊。記事にしましたので宜しければご覧ください。
変化への対処
- スペンサー・ジョンソン(著)、門田美鈴(翻訳)『チーズはどこへ消えた?』(扶桑社):全体で100ページ足らずと短いものの、変化への適応というテーマで長らくベストセラーの座にある本です。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- スペンサー・ジョンソン(著)、門田美鈴(翻訳)『迷路の先には何がある?――「チーズはどこへ消えた?」その後の物語』(扶桑社):『チーズはどこへ消えた?』の続編です。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪