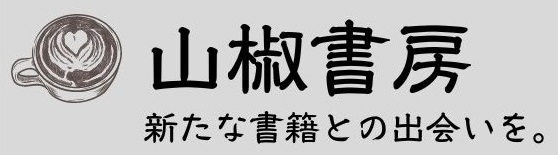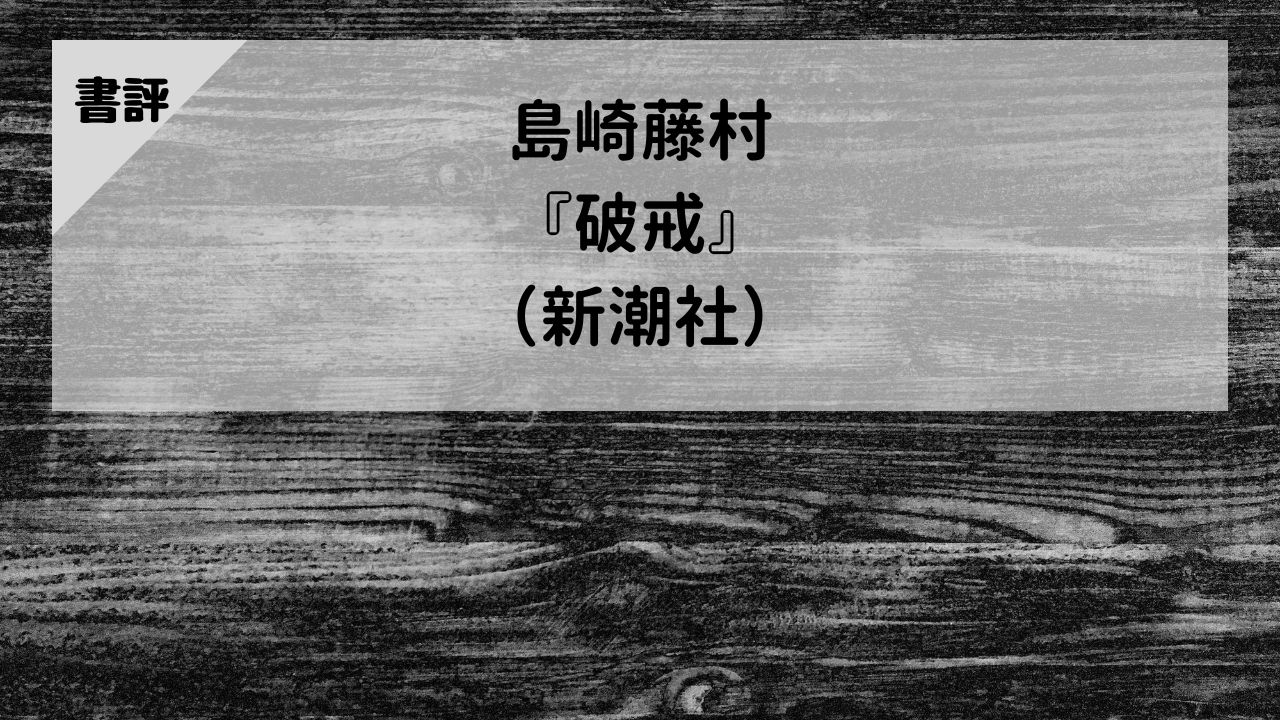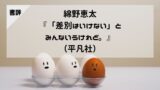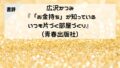皆さんには、教科書で習ったから名前は知っているけど読んだことがない本はありますか?
私はあります。それはもう大量に。お恥ずかしい…。
というのも、私が読書に目覚めたのは大学を卒業して社会人数年目の20代半ば。学生時代に読んでいた教科書のなかに登場する文学作品は、あくまで試験対策のために暗記するものだったのです。
今回ご紹介するのは、そんな教科書に登場する超有名な作品。被差別部落出身の主人公を描く島崎藤村『破戒』です。
実は、島崎藤村にはちょっとした苦い思い出がありまして。未だに、にわか読書家の域を出ていない私ですが、実は大学4年生のときにも読書に挑戦して何冊か小説を手に取ったのです。それが、橋本治『桃尻娘』と島崎藤村『夜明け前』。
『桃尻娘』は連作短編集なので、読書に慣れていない私でも読了することができました。が、文庫本で全4冊の長編『夜明け前』は残念ながら1冊目で挫折。実は、その頃から今に至るまで、島崎藤村には少し敷居の高さというか…読み通せなかった引け目とか申し訳なさみたいなものがあったのです。
時は流れ、令和の時代。昨今は芸能事務所問題などで人権尊重が声高に叫ばれるようになりました。国連が掲げる世界人権宣言には、以下の記述があります。
第二条
引用元:世界人権宣言テキスト(国際連合広報センター)
- すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
- さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
「社会的出身、…、門地…いかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」
社会的出身、門地…。私は被差別部落問題が存在していることは知っていたのですが、これまで家族や地域など周囲で話題にあがったことはほとんどありませんでした。実際のところはよく知りませんが、どちらかというと関東首都圏出身の人は被差別部落問題に疎い、ということを聞いたことがあります。まさしく私は疎かった。
そこで思い出したのが、過去に挫折した島崎藤村の『破戒』です。長編小説ですが、こちらは夜明け前と比べてページ数が随分少ない。これなら読み通せるかも…!と島崎藤村の作品に再挑戦することにしたのです。
『破戒』はストーリー展開もさることながら、文学史的な観点でも外せない一冊でした。ということで、前置きが長くなりましたが、本作が社会に与えた影響や文学史的観点から中身を見ていきましょう。
こんな方にオススメ
- 被差別部落などの差別問題に関心がある方
- 明治時代の日本の風景や価値観が知りたい方
- 長く読み継がれている作品の歴史に興味がある方
テーマは被差別部落問題?
第一の観点として確認しておきたいのは、この小説のテーマです。先に少し述べたとおり、本作は「被差別部落」出身の主人公、瀬川丑松を巡る一連の物語です。
士農工商の下位に置かれ賤民と呼ばれた人々は、明治4年(1871年)、解放令により身分・職業ともに平民同様ということになりました。しかし、「新平民」という蔑称でその後も差別される状況が続きました。現代においても、残念ながらまだ差別は存在しています。「被差別部落問題」という言葉が存在することがその証左といえるでしょう。
以下のような記述があります。物語序盤、主人公の下宿先で部落出身者が追い出されてしまう場面にて。
今の下宿にはこういう事が起った。半月程前、一人の男を供に連れて、下高井の地方から出て来た大日向という大尽、飯山病院へ入院の為とあって、暫時腰掛に泊っていたことがある。入院は間もなくであった。もとより内証はよし、病室は第一等、看護婦の肩に懸って長い廊下を往ったり来たりするうちには、自然と豪奢が人の目にもついて、誰が嫉妬で噂するともなく、「彼は穢多だ」ということになった。忽ち多くの病室へ伝って、患者は総立。「放逐して了え、今直ぐ、それが出来ないとあらば吾儕挙って御免を蒙る」と腕捲りして院長を脅すという騒動。いかに金尽でも、この人種の偏執には勝たれない。
引用元:島崎藤村『破戒』(新潮社)
「大尽」とはお金持ちのことで、「内証」は経済状態のことを意味します。一部古風な表現があるものの、明治期という100年以上前に発表された作品でありながら、比較的現代文に近い文章であることがよく分かるでしょう。余談ですが、随所に登場する信州の美しい風景描写も見事です。
本作では、全編を通して部落出身者に対する厳しい差別感情、排他主義が生々しく描かれています。もちろん、被差別部落問題は極めて重要なテーマです。ただ、本作が出版当時話題となり、さらに現代においても長く読み続けられている理由は、差別問題だけではないような気がするのです。
社会問題を扱う小説か、自己告白の小説か
作品の後に収録されている解説を読んでいると、解釈は文芸評論家によってさまざまであることが分かります。そして、私が感じたように、本作は「特殊な出自を持つ主人公がその社会的偏見にどう向き合うか」という点だけが本書の主軸ではないことが分かってきます。
もう一つの主題としては、「自我の秘められた苦悩の告白」。本書で主人公の丑松は、自分の出自を明かすか否か、大いに葛藤を抱き悩む日々を過ごします。揺れに揺れる決意と、言動の不一致。こうした丑松の挙動からは、まさに合理的ではない人間の生き様を見せつけられ、リアリティがあります。
さらに興味深いのは、島崎藤村の人生との関連性です。島崎藤村が歩んだ人生と比較してみると、物語の展開に藤村自身の葛藤や人生経験が反映されている様子が見えてくるのです。
誰しも、大なり小なり公にしにくい秘密というものがあるでしょう。したがって、出自に関係なく「自己告白というテーマで本書は語られているのではないか」という見方が可能です。
実際、小説を最後まで読めば分かりますが、社会問題としての被差別部落差別は残念ながら解決しない形で本作は終わります。それでありながら、一種美談のような余韻も残している点を踏まえると、安直に社会派小説とは評しがたい。
以上の議論がありつつも、文芸評論家の平野謙氏は解説にて以下のように述べています。
しかし、『破戒』を社会的なプロテストとして読むのが正統か、自意識上の苦悶として読むのが正統か、という問題の設定自体が実はおかしいのではないかと思う。自意識上の苦悶として読む視点と、丑松に仮託した作者自身の自己告白として読む視点との相異は、歩一歩のへだたりにすぎないともいえるが、丑松の「告白」に重点があるのであって、「部落民」はそれを重からしめるための一手段にすぎないという読みかたや、告白しようか隠そうかという丑松の心の動揺がまるでその恣意によって決定されるみたいな読みかたはやはり『破戒』という作柄に即したものとはいいがたいだろう。
引用元:島崎藤村『破戒』(新潮社)
本作はすでに著作権が切れているため、青空文庫などで無料で読むことができます。しかし、できれば出版されていて解説が付されているものを読むのがよいでしょう。解説を読むことによって、何倍も深く作品を考えるきっかけを得ることができるからです。解説こそ、現代に生きる私たちに実りをもたらしてくれるのです。
出版を巡る経緯も複雑
文学史上、出版を巡る歴史も興味深いです。
現在出版されている新潮文庫版は初版本の記述をそのまま載せていますが、作中には事実無根の歴史を記した表現や、明らかな差別表現が登場します。島崎藤村自身は本作において差別を助長する意図はなかったものと思われますが、読み手により確固たる差別意識が惹起される可能性もあるわけです。
こうした懸念に対して作品自体が常に批判の的となっていたことは想像に難くなく、10年以上ものあいだ絶版となります。そして、その後「これは過去の物語である」と著者が明言し大きく表現を見直したうえで、復刊することになるのです。たしかに、部落解放令そのものは島崎藤村が生まれる1年前に出されています。
しかし、この改訂本における修正がすこぶる評判が悪い。「『破戒』と差別問題」のなかで北小路健氏は以下のように述べます。
(中略)はっきりいうと改訂版は改悪版である。文芸作品としてもそうだし、心中の差別観をそのままに、いかにも理解ある者のごとく「穢多」を「部落民」とし、「新平民」を「部落生れのもの」とすることで水平社の人々の目を外らせたのは、結果として狡猾であったといわれても致し方あるまい。そして藤村自身は、自己欺瞞を敢えて行った。そうしてまでも『破戒』をこの世に残したかったのだ、それほどの愛情を持ちつづけていたのだという見方もあり得よう。しかし、改訂本が改悪本となることを、いちばん知っていたのは彼自身であったはずだ。
引用元:島崎藤村『破戒』(新潮社)
以上の経緯で、現在では初版本が広く読み継がれています。いま私たちが手に取っている作品は、当事者団体からの批判を受け表現の修正がなされたあと、その社会的重要性を鑑み、再び差別的表現をそのままに残している。こうした歴史を知ることで、本当の意味での差別撤廃が進むことを願っています。
関連書籍
- 綿野恵太『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社):「差別」に対する反対運動について、当事者以外の人間が声を上げることについて政治的・経済的・社会的な背景から迫り、差別・反差別の本質を明らかにしようとする一冊です。良質な評論を求める方に絶賛オススメです。記事にしましたので宜しければご覧ください。
- 橋本治『桃尻娘』(講談社):橋本治氏のデビュー作です。私は大学生の時に、こちらの橋本治氏の小説を初めて読みました。「人間を深く理解したうえで書かれた作品だなぁ…」と当時感じたことを、今でも覚えています。
- 島崎藤村『夜明け前 第一部(上)(下) 第二部(上)(下)』(新潮社、岩波書店):全4巻の『夜明け前』は、島崎藤村の父をモデルに幕末・明治維新の激動期を描きます。「木曾路はすべて山の中である」で始まる書き出しも有名ですね。
- 島崎藤村『春』(新潮社):島崎藤村の自伝的な小説です。登場人物はそれぞれモデルがいるので、明治期の文学がお好きな方はそういう意味でも楽しめると思います。
- 森鴎外『山椒大夫・高瀬舟』(新潮社):島崎藤村と同時代に活躍した文豪はたくさんいますが、ここでは森鷗外を挙げておきます。こちらの作品も、名前は知っているけど読んだことがない、という方が一定数いることでしょう(実は私もです)。高瀬舟の取り扱うテーマは現代に通ずるはずで、今後も色あせない名作であり続けると思います。
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪