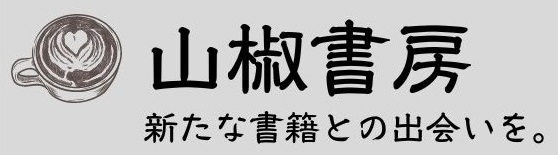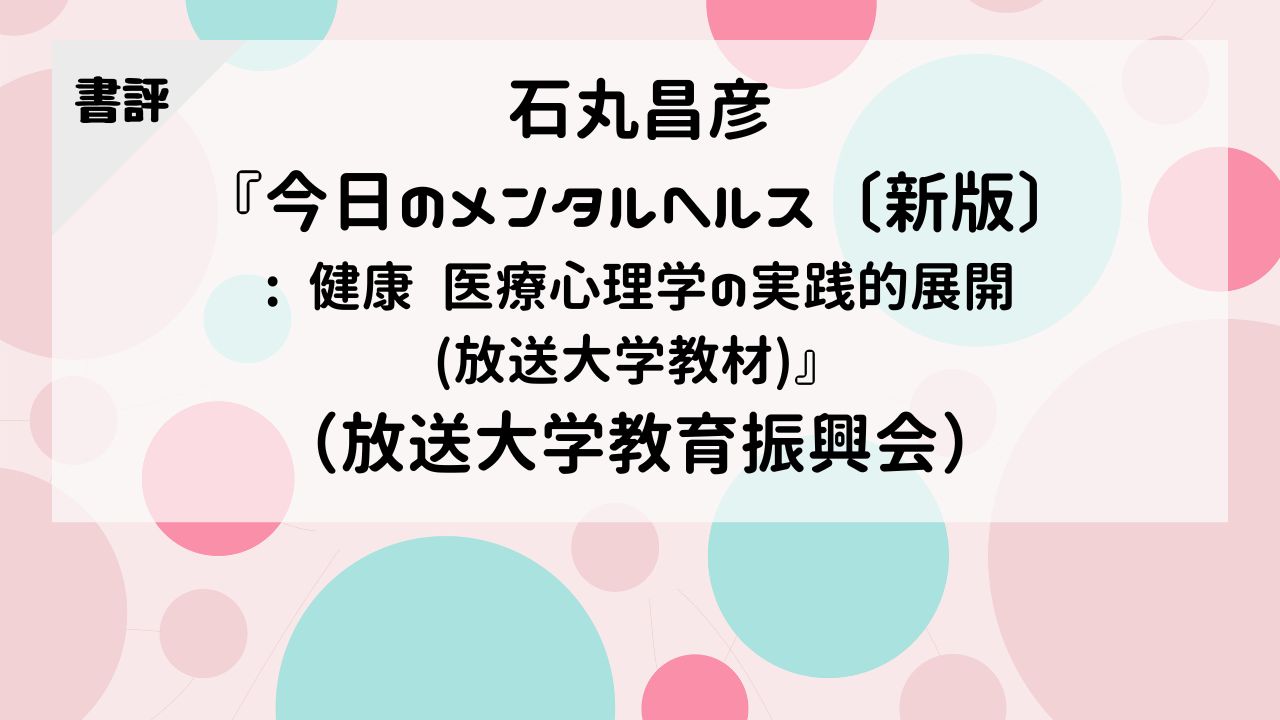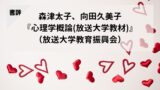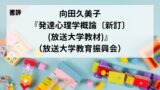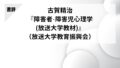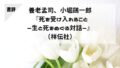先日ご紹介した「発達心理学概論('17)」では、周囲で新たな命が生まれつつあったことをお伝えしました。この出来事を機に、私は人間の発達という分野に関心を持ち「発達心理学概論('17)」の履修を決めたわけですが、同様の理由で履修のきっかけを得た科目がもう一つありました。
それが、今回ご紹介する「今日のメンタルヘルスー健康・医療心理学の実践的展開ー('23)」です。こちらの科目、目次を見てみると…なんと! 周産期から老年期にいたるメンタルヘルスについて、4回にわたって説明のページが割かれているではありませんか!
この目次から想像するに「発達心理学と併せて学ぶことで理解がさらに深まるのでは!?」と私はひらめいたのです。
私は、健康心理学・医療心理学という分野にはこれまであまり馴染みがなかったのですが、本科目の担当教員に書かれた石丸昌彦氏のお名前に注目しました。思い出されたのは2023年1月28日に開かれた公開講演会、「メンタルヘルスと死生観 ~ スピリチュアリティをめぐって考える」。この講演会に参加した私には、石丸氏の穏やかで理知的な話し方が記憶に残っていました。
ということで、身辺環境の変化と講師への期待から私は「今日のメンタルヘルスー健康・医療心理学の実践的展開ー('23)」を履修することに決めたのでした。
本科目は、何よりも放送授業が大変素晴らしいです。民放のようにカジュアルで親しみやすい雰囲気を残しつつも、NHKのようにエビデンスに基づく正確さも感じさせるテレビ番組のようでした。あのコシノジュンコさんも放送授業のなかでインタビューに登場していて、「おおっ!」と思わず声を出してしまいました。
そして、目次をよくよく見ると、取り扱う内容も人間の一生に関するものだけではなくて、職場のストレスや精神疾患、災害時のメンタルヘルスといった、より身近で実務的なテーマも含まれていました。
今回は、メンタルヘルスの維持・充実に焦点を当てて学ぶ「今日のメンタルヘルスー健康・医療心理学の実践的展開ー('23)」の印刷教材(テキスト)をご紹介します。
書籍は全国の書店などで購入できます。放送大学生でない方も、本科目の講義はBS放送などのテレビで視聴可能です。詳しい視聴方法は以下をご参照ください。
放送大学科目の書評記事のまとめはこちら
放送大学の科目についての書評記事は以下にまとめました! ご興味あればご参照ください♪
本講座の基本情報
本講座「今日のメンタルヘルスー健康・医療心理学の実践的展開ー」は、放送大学で開講されている科目です。
- 2023年度開設
- 放送授業(テレビ配信)
- 生活と福祉コースの専門科目
具体的なシラバスはこちらからご参照ください。
放送授業はテレビで公開されており、書籍はAmazonほか各書店でお買い求めいただけます。各地域におけるテキスト取扱書店は下記をご参照ください。
こんな方にオススメ
- 人間の一生のあいだに生じる健康上の課題について理解を深めたい
- 職場のメンタルヘルスを考えたい
- 災害時のメンタルヘルスを学びたい
目次
本書の目次は下記のとおりです。全15回の放送授業に沿った章立てとなっております。
1 メンタルヘルスとは何だろうか
2 ライフサイクルとメンタルヘルス(1)
周産期・乳児期・幼児期
3 ライフサイクルとメンタルヘルス(2)
児童期・思春期・青年期
4 ライフサイクルとメンタルヘルス(3)
成人期
5 ライフサイクルとメンタルヘルス(4)
老年期と人生のしめくくり
6 ストレスの理論
7 職場とストレス
8 ストレス・コーピングの実践
9 精神疾患(1)
心の病とはどんなものか
10 精神疾患(2)
脳の機能変調と精神疾患
11 精神疾患(3)
依存という病~アルコール・薬物・インターネット
12 精神疾患(4)
ストレスとストレス反応
13 災害時とメンタルヘルス
14 グリーフケア
15 自殺とその予防
老年期のメンタルヘルス
人間の一生におけるメンタルヘルスについてですが、「発達心理学概論('17)」では人の誕生・成長に関する内容を記載しましたので、ここでは老年期について取り上げます。数字ばかりの引用となりますが、まずは少子高齢化を感じさせる統計結果を見てみましょう。
高齢者の生活環境はめまぐるしく変化している。昭和55(1980)年には3世代世帯の割合が多かったが、平成27(2015)年には夫婦のみの単独世帯が約3割で、単独世帯と合わせると半数を超える。また、子どもとの同居が減り、一人暮らしの高齢者が増えてきている。65歳以上の一人暮らしは男女ともに増加傾向にあり、昭和55(1980)年には男性約19万人、女性約69万人、65歳以上人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%であったが、平成27(2015)年には男性約192万人、女性約400万人、65歳以上人口に占める割合は男性13.3%、女性21.1%となっている。また65歳以上の世帯についてみると、平成31(2019)年、世帯数は2,558万4000世帯と、全世帯(5,178万5000世帯)の49.4%を占めている。
引用元:石丸昌彦『今日のメンタルヘルス〔新版〕: 健康 医療心理学の実践的展開(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
私の知人のうち、65歳以上で元気に活動している方はたくさんいらっしゃいます。とはいえ、2019年時点で65歳以上の世帯が全世帯の約5割を占めていたという事実はなかなか衝撃的でした。65歳以上女性の一人暮らしが約400万人、というデータも割とインパクトのある数字です。これが2015年時点の統計結果ですから、当時から10年経過している今はさらに増加していることでしょう。
コロナ禍を経て、私は通勤のために電車を再び使うようになりました。車内を見渡すと60代以上と思われる方がやはり多い印象を受けます。長寿化が進んだというのはもちろんですが、それに併せて家族のあり方が変わってきたというのは、介護を含む課題を考えるうえで外してはならない観点なのでしょう。
本書では、仕事第一で働いてきた夫が退職後に家庭でどのように生活するか困惑する姿や、子育てが終わった妻が夫に理解されない孤独感を感じる姿が事例として書かれています。夫婦や家族の形は多様化しているので画一的なやり方はなさそうですが、本書で書かれている知見は考えるヒントに富んでいました。
うつ病の定義
そして、本書で驚いたのは「うつ病」の定義です。「うつ病」という病気の認知度はかなり高く、日本人の多くが見聞きしたことがあるでしょう。自分自身や家族、職場の方など身近な方が診断されたという方も少なくないことと思います。
それほどよく知られているうつ病ですが、その概念が登場した19世紀末の診断基準はちょっと違っていたようで。
同時にクレペリンの診断体系において、うつ病・躁うつ病は脳の機能変調による内因性のものを指していた。辛い出来事やストレス体験によるものは、了解可能な心因性の反応であってうつ病とはされなかった。理由もないのにひどく気分が沈むものこそ「病気」であり、脳の機能変調の結果であると考えられたのである。
引用元:石丸昌彦『今日のメンタルヘルス〔新版〕: 健康 医療心理学の実践的展開(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
これに対して今日のDSMが定義するうつ病は、より軽症のものを含む広い概念となっている。さらにDSMは症状を重視する立場をとり病気の原因を問わないので、内因性のものもストレス性のものも、区別なくそこに含まれることになる。うつ病の診断にあたってストレス体験や心理的なきっかけといった「原因」は、あってもよいがなくてもかわまない。今日ではストレスの影響が強調され、「うつ病」即「ストレス反応」と思い込みがちであるので注意しておきたい。
元々うつ病は内因性(原因不明とされる脳の機能的変調。統合失調症など)の反応であって、心因性(心理的な原因によって起こる精神的な変調。PTSDなど)のものではなかった、というのです。
現在ではうつ病は、たとえば仕事との関わりでいえば「上司からのパワハラと同僚からのいじめを受けて…」「長時間残業の結果…」「会社が倒産して家族ともうまくいかなくなって…」などの原因があって病気になる、という文脈で語られることが多いように思います。なんにせよ「理由」を挙げて説明できるという印象がありました。
それが、元々は「理由もないのにひどく気分が沈む」というものがうつ病だったと。これは驚きでした。続けて、「『うつ病』即『ストレス反応』と思い込みがちであるので注意しておきたい。」というのはまさに自分に対して指摘されているかのようでした。
精神疾患の診断基準としてよく知られるDSMは定期的に改訂されます。DSMも時代の流れに合わせて変わってきたこと、そしてこれからも変わっていくことを考えると、診断基準を念頭にしつつも、目の前の相談者と真摯に向き合い耳を傾けていく営みの重要性を感じさせられました。
災害時のメンタルヘルス
最後に、災害時のメンタルヘルスについても少し触れたいと思います。日本では、地震による災害だけを挙げてみても、阪神・淡路大震災(1995年)、新潟県中越地震(2004年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2017年)、能登半島地震(2024年)と約30年のあいだに多数の災害に見舞われています。豪雨や噴火による災害を含めると、さらに災害件数は増えるでしょう。
災害時には、それまで心身が健康だった方も体調を崩すことが少なくありません。さらに、子ども、高齢の方、日本語が話せない方、精神疾患を抱える方などは、平時と異なる特別なケアが必要になります。
…というふうに、一般市民を対象にした被災時支援を考えるのはもちろん重要ではあるのですが、支援者に対する支援も重視されるべきでしょう。以下の引用箇所が新たな視点を与えてくれます。
救援者は困難な状況や危険に陥っている人を助ける人(たとえば警察官、消防士、救急救命士、自衛官など)であり、支援者は力を貸して助ける人(基本的には災害時に被災者を支援するすべての職種、たとえば前述の救援者を含み、医療職、行政職、教職員、ボランティアなど)と、ここでは便宜上定義する。救援者は自分も被害に遭う、または凄惨な現場を目撃する可能性のある状況で、危険な状況の中に飛び込んで救助するイメージがある。支援者はそのような人も含めて、前線で支援をしたり、後方支援として、行政、医療、ボランティアなど被災者を助けるすべての人々とここでは考える。
引用元:石丸昌彦『今日のメンタルヘルス〔新版〕: 健康 医療心理学の実践的展開(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
(中略)
救援者がその後、うつ病、ASD、PTSD、アルコールや薬物の乱用などを発症する率は、一般の被災者よりも高いことを示した報告が数多くある。
以前、何かの勉強会で「支援者支援」という言葉を初めて聞きました。災害において、支援者は被災者でありながら市民のために奔走するという点で、心身に大変な負荷がかかり続けます。自宅や家族を失いながら、街の人々のケアをしていく支援者ももちろんいることでしょう。
本書では、こうした救援者・支援者はこれらの職に就いて3ヶ月ほどで、一般の人が一生にわたって被るストレスを経験する、とも書かれていました。被災地でのボランティア活動は阪神・淡路大震災を機にかなり広まった印象がありますが、現地に向かう場合の心構えとしても覚えておくべきポイントであると強く心に留めました。
放送大学科目の書評記事のまとめはこちら
放送大学の科目についての書評記事は以下にまとめました! ご興味あればご参照ください♪
関連書籍
- 森津太子、向田久美子『心理学概論(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):心理学を学ぶ方は、まずこちらの書籍からスタートすると良いです。2024年度には改訂版が登場し、よりパワーアップしています。2018年度版について記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 向田久美子『発達心理学概論〔新訂〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):「発達」という用語は子どもだけを対象とした概念ではありません。人の一生における「発達」に関心がある方はこちらも是非。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 日本産業カウンセラー協会(編)『産業現場の事例で学ぶ カウンセラーのためのスーパービジョン活用法』(金子書房):今回は割愛しましたが、職場のメンタルヘルスは産業分野でのカウンセリング理解にも役立ちます。日本産業カウンセラー協会が編纂したスーパービジョン活用法についての一冊は、新米カウンセラーもベテランカウンセラーも、スーパービジョンを活用する上で事前に知っておきたい知識があるだけでなく、第Ⅲ章の事例が充実しています。すでに支援に携わるお仕事をしている方、将来に向けて勉強中という方、各々得るものがある本ではないかと。
- 高橋晶・高橋祥友(編)『災害精神医学入門―災害に学び、明日に備える』(金剛出版):「今日のメンタルヘルスー健康・医療心理学の実践的展開ー('23)」で講師を務めた高橋晶氏と高橋祥友氏による被災者の心のケアについての一冊。非専門家のボランティアにも役立つ内容です。災害が多い日本では、災害精神医学が今後さらに重視される分野になることでしょう。
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪