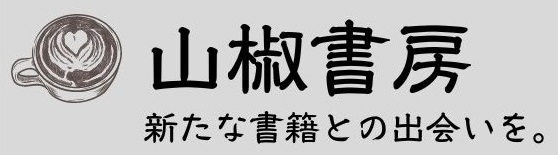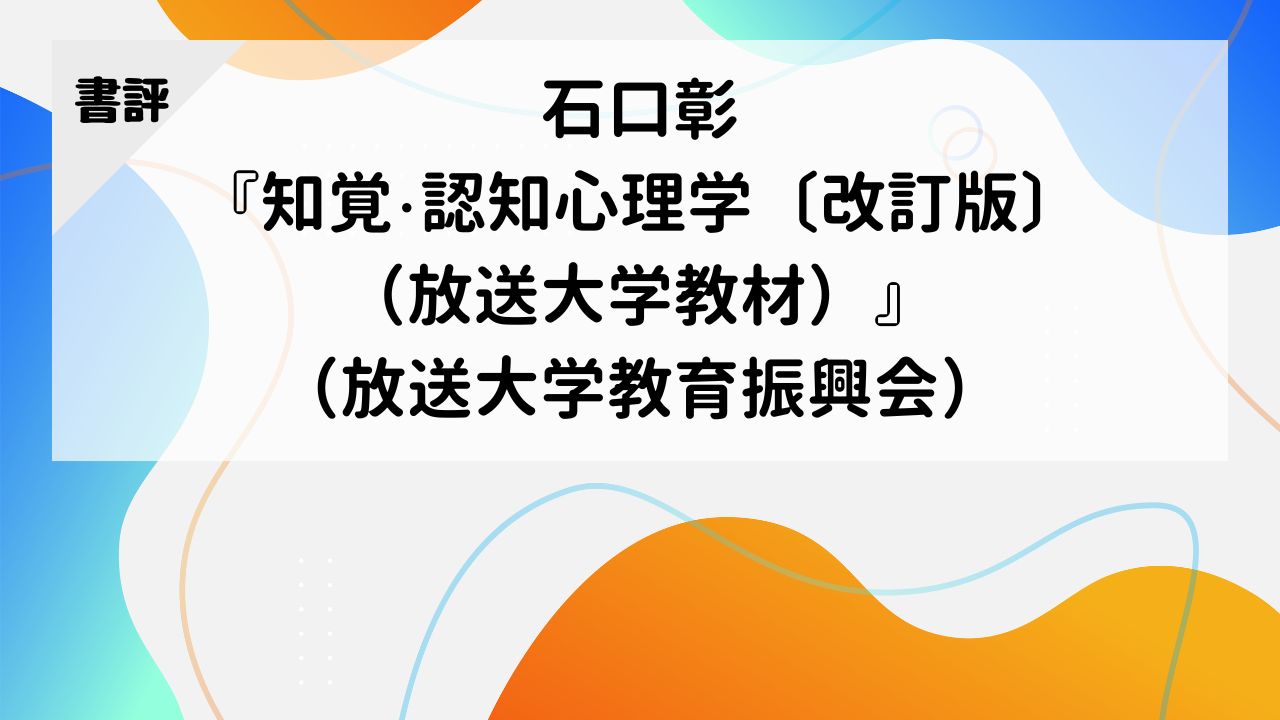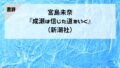放送大学に在籍して3年目の2025年。公認心理師関連科目のシラバスを眺めていた私が目を留めたのは、生理的・神経学的な観点から学ぶ「神経・生理心理学」でした。
心理系の学生は高校時代に文系を選択したというケースが多いためか、理系の要素がある学問は不得手という傾向があります。実は、私はかつて通っていた4年制大学の卒業論文で生理心理学の要素を含むテーマで研究を行ったこともあり、わりと神経・生理心理学に関心があるタイプ。とはいえ、あれから十何年…。再びの学び直しにやや及び腰でした。
そんななか、他の科目のシラバスも眺めていたところ「神経・生理心理学」と学問領域が近そうな科目を発見!! それが、「知覚・認知心理学」です。ということで、2科目を同時に履修することに決めました。この判断は良かったようで、両科目を同時に学習することで予習と復習を兼ねて理解を深めることができたと思います(超オススメ)。
さて、この「知覚・認知心理学」ですが、主任講師の石口彰先生は講義内容にさりげないユーモアを混ぜ込みながら説明してくださいます。放送授業のなかで、簡易的ではあれ実験に参加できるのも楽しかったです。そして、何より印象に強く残ったのが、講義が上品な挨拶で終わること!
今回は、「考える」という観点から人の感覚・知覚や認知機能について整理した「知覚・認知心理学」の印刷教材(テキスト)をご紹介します。
書籍は全国の書店などで購入できます。放送大学生でない方も、本科目の講義はBS放送などのテレビで視聴可能です。詳しい視聴方法は以下をご参照ください。
放送大学科目の書評記事のまとめはこちら
放送大学の科目についての書評記事は以下にまとめました! ご興味あればご参照ください♪
本講座の基本情報
本講座「知覚・認知心理学」は、放送大学で開講されている科目です。
- 2023年度開設
- 放送授業(テレビ配信)
- 心理と教育コースの専門科目
具体的なシラバスはこちらからご参照ください。
放送授業はテレビで公開されており、書籍はAmazonほか各書店でお買い求めいただけます。各地域におけるテキスト取扱書店は下記をご参照ください。
こんな方にオススメ
- 「考える」ということについて科学的な知見を得たい
- 公認心理師を目指している
- 感情や言語など知覚・認知機能との関連を学びたい
目次
本書の目次は下記のとおりです。全15回の放送授業に沿った章立てとなっております。
1 知覚・認知心理学の概要
2 知覚・認知の神経的基盤
3 知覚・認知心理学の研究法
4 感覚のしくみ
5 知覚のしくみ
6 注意のしくみ
7 記憶のしくみ
8 日常の記憶
9 推論のしくみ
10 問題解決と熟達化
11 判断と意思決定
12 知覚・認知と言語
13 知覚・認知と感情
14 知覚・認知の発達
15 知覚・認知の障害
「考える」ことについての科学
「知覚・認知心理学」というタイトルは、本音を言わせてもらうと、違和感を拭いえない。
引用元:石口彰『知覚・認知心理学〔改訂版〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
さて、知覚心理学や認知心理学を過去に学んだことがある方なら、本科目の科目名を見て若干の違和感を抱くことでしょう。他ならぬ私もそうでした。というのも、もともとは知覚心理学と認知心理学は全く別の学問領域として独立に存在していたのです。
前者はどちらかといえば基礎系の心理学、後者はどちらかといえば応用系の心理学。私が4年制大学に通っていたときも、当然別々の科目でした。それが、本講義ではなんと合体してしまっているのです。
二つの別々の科目が合体した契機は、公認心理師の登場とのこと。
流れが変わったのは、やはり、「公認心理師」の登場であろう。「公認心理師試験設計表(ブループリント)」には、大項目7「知覚及び認知」、中項目「(1)人の感覚・知覚の機序及び障害」、「(2)人の認知・思考の機序及びその障害」とあり、まさに「知覚・認知心理学」である。この「公認心理師」の登場以来、多くの大学の授業科目は、上記のブループリントに則り、知覚心理学や認知心理学を「知覚・認知心理学」と、内容も含めて、改編した。
引用元:石口彰『知覚・認知心理学〔改訂版〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
付け加えるならば…個人的には、研究テーマに知覚心理学を掲げる教員より、認知心理学を掲げる教員の方が圧倒的に多いのでは、と想像しています。母校で知覚心理学の教員が定年退職を間近に控えていたときは、後任者が来るかちょっと心配…なんて噂も小耳に挟んだものですから。
したがって、教員確保の観点から、公認心理師の新設に併せて知覚心理学と認知心理学を同じ科目にまとめてしまうことで、大学側にとっても運営コストの面で多少メリットがあったのではという考えを私は持っています(大学側の事情に明るい訳ではないので、私の勝手な推測ということでご理解ください)。
経緯はなんであれ、この別々の科目を「考える」ことの科学という形でまとめているのはなるほどな、と思いました。知覚心理学で取り扱う内容は「無意識的に考える」、認知心理学で取り扱う内容は「意識的に考える」。統一感を持った言葉でまとめているのは、さすがです。こうして科目名に対する違和感はかなり和らぎました。
放送授業も印刷教材も丁寧に作られている
放送授業では映像を用いた実験があり、受講者が参加することで実感を伴った理解が促されます。まさに、テレビ形式の利点を生かしています。
しかも、初学者が置いてけぼりにならないように、新しく登場した用語についてはスライド(パターン)を見せるだけでなく、説明した内容について「ココとココですね」と丁寧に念押ししてくださいます。未知の学問ほど、「いま、提示された資料のどれについて説明してるの…? わからないよ…」と迷子になってしまうことは意外と多いものです。細かい点ではありますが、念押しでの説明は本当に親切です。
そしてそして、講義は常に「ごきげんよう、さようなら」で終わります。この終わりの挨拶がとても上品で、最初はビックリしました。講師陣のご経歴を見るに、みなさんお茶の水女子大学と関わりがある模様。もしかしたらお茶の水女子大学では常識的な挨拶なのかも? なーんて想像しながら受講していました。なんにせよ「さようなら」の前に「ごきげんよう」が来るのがとても良いです。
印刷教材では、章末の学習課題が充実しています。斜め読みしただけでは解けない内容で、理解度促進に大変効果的です。一例として、第10章(問題解決と熟達化)の章末の学習課題はこんな感じ。
学習課題
課題4 戦術的学習と戦略的学習に関して、本章の例とは別な例を用いて、説明しなさい。学習課題のポイント
引用元:石口彰『知覚・認知心理学〔改訂版〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
課題4 まずは、戦術的学習と戦略的学習に関して、その違いがわかるように説明する。「再生産的思考」と「生産的思考」との関連性に触れても良い。例は、なるべく身近なものを挙げると、わかりやすい。
印刷教材に解答例は載っていません。あくまで解答の「ポイント」だけが載っています。オープンクエスチョン的な要素が含まれる課題が多く、学習者によってさまざまな回答があり得ます。院試や高度な資格試験を目指して受講している方にとっては、役立つ問題集となることでしょう。
プロスペクト理論も認知心理学で学べる
私のなかで認知心理学という学問から連想されるのは、プロスペクト理論です。プロスペクト理論で知られるカーネマン&トヴェルスキー両氏の研究は、心理学の知見を行動経済学という分野に発展させ、カーネマン氏もノーベル経済学賞を受賞しました。この記事を読んでいる方のなかにも「プロスペクト理論は聞いたことがある」という方もいることでしょう。
主流としての期待効用理論に対して、様々なパラドックスが生じる人間の実際の意思決定は、当初は例外的なものとして扱われていた。しかし、1970年代以降、流れは変わった。上記のように、人間の意思決定行動の特性に対し、期待効用理論が論破できない事態が注目された。
引用元:石口彰『知覚・認知心理学〔改訂版〕(放送大学教材)』(放送大学教育振興会)
そこに登場したのが、人間の意思決定行動を踏まえたカーネマンとトヴェルスキー(Kahneman & Tversky, 1979)のプロスペクト理論(prospect theory)である。プロスペクトとは、「見込み」のことである。その理論は、行動実験を踏まえた、主として次の3つの特徴を有する。
プロスペクト理論が登場するまでの経緯と、その理論の詳細は本書を確認いただければと思いますが、働きながら勉強しているという社会人学生は、この理論をよく理解しておくと良いかと思います。意思決定に関する理論は、生活に直結する可能性がありますから。
なお、ダニエル・カーネマン氏は2024年3月に90歳で逝去しました。それから1年後、ウォール・ストリート・ジャーナル(The Wall Street Journal:WSJ)では、なんとカーネマン氏がスイスの自殺幇助施設にて、医師の助けにより自ら命を絶つことを選択してその生涯を閉じた、というエッセイがJason Zweig氏により寄稿されています。
Shortly before Daniel Kahneman died last March, he emailed friends a message: He was choosing to end his own life in Switzerland. Some are still struggling with his choice.
引用元:Jason Zweig. (2025, March 14). The Last Decision by the World’s Leading Thinker on Decisions. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com/arts-culture/books/daniel-kahneman-assisted-suicide-9fb16124
これは私にとって少し驚きを禁じ得ませんでした。心理学を含め世界に大きな影響を与えた研究者の人生について、思いを巡らせるばかりです。
放送大学科目の書評記事のまとめはこちら
放送大学の科目についての書評記事は以下にまとめました! ご興味あればご参照ください♪
関連書籍
- 相良奈美香『行動経済学が最強の学問である』(SBクリエイティブ):人間は合理的ではない判断をくだしがちです。本書は15万部突破のベストセラー。
- 髙瀨堅吉『神経・生理心理学(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):本記事ではあまり言及しませんでしたが、神経学・生理学的知見はこちらで理解を深めることができます。「知覚・認知心理学」と一緒に受講すると理解が深まります。
- 坂井建雄、岡田隆夫『人体の構造と機能〔改訂版〕: 人体の構造と機能及び疾病A(放送大学教材)』(放送大学教育振興会):生物学的・解剖学的な観点での基礎知識を得たい方は、こちらの一冊が有用です。記事を書きましたので、宜しければお読みください。
- 北岡明佳『世界一美しい錯視アート トリック・アイズプレミアム』(カンゼン):本記事では割愛しましたが、知覚心理学といえば錯視がよく知られています。なかでも、立命科大学の北岡明佳先生が有名です。芸術的なものも多々ありますので、ご興味あれば調べてみましょう。ちなみに、先生のホームページでは、さまざまな錯視を眺めることができます。新作も定期的に登場し続けています。すごい!
最後までお読みいただき有り難うございました!
♪にほんブログ村のランキングに参加中♪